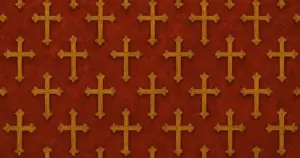教会時論 二〇二五年九月二十八日 日曜日「パレスチナの苦悩・分断する社会・多様な性――平和と尊厳を問い直す責務」

はじめに 平和と尊厳を守るということ
いま世界のあらゆる地域で、人間の尊厳が問われている。パレスチナの地では、幾万もの人命が奪われ、生活の基盤が破壊され続けている。ガザの瓦礫の下から救いを求める声に耳をふさぐことは、もはやできない。国際社会が国家承認を通して「二国家共存」の意思を示す中、日本政府は一歩を踏み出せずにいる。その沈黙の重さを私たちは真剣に受け止めなければならない。
一方、私たち自身の社会に目を向ければ、言葉や表現をめぐって人々が互いに断罪し合う風潮が広がっている。キャンセルカルチャーと呼ばれる現象は、もともと不正義をただす市民の声から始まった。だが今や、誤りを犯した者に回復の道を残さず、社会から排除することに快感を見いだすような危うさを帯びている。他者の過去を糾弾することで安心を得ようとする姿は、正義の名を借りた残酷さに通じるものがある。そこにこそ、私たちの社会が抱える深い分断の影が映し出されている。
さらに日本では、札幌家裁が性同一性障害特例法の「外観要件」を違憲と判断した。性別変更のために手術を強いることは、憲法が保障する「個人の尊重」に反すると裁かれたのである。この決定は、性的少数者の人権を守るために社会がいかに変わるべきかを突きつけるものだ。法制度は人の多様な生を受け入れる器でなければならない。外観を一律に揃えさせるのではなく、一人ひとりの存在そのものを尊重することが求められている。
三つの出来事は、性質も文脈も異なる。遠く中東での戦争、現代社会の文化的摩擦、そして国内の司法判断。しかしそれらを貫く軸は一つである。すなわち「いのちと尊厳を守る」という問いだ。戦火の下で命を落とす子どもも、社会的糾弾の中で孤立する人も、制度の壁に阻まれて自分らしく生きられない人も、いずれも声なき声を上げている。その声に応えることは、私たち信仰者に託された使命にほかならない。
「真理はあなたがたを自由にする」(ヨハネ八・三二)。真理とは、苦しむ隣人を直視し、沈黙を破って共に歩む勇気である。忘却や無関心の陰に身を隠すとき、私たちは自由を失い、未来を閉ざす。しかし痛みに向き合うとき、そこにこそ神が共におられることを知る。平和と尊厳を守る責務は重い。だが、その道を歩むとき、教会はこの世界のただ中で福音の光を証しする共同体となるのである。
一.パレスチナ国家承認をめぐる日本の責任
九月下旬、国際社会は再び中東和平の行方に注目した。英国、フランス、カナダが先進七カ国(G7)で初めてパレスチナを国家として承認したのである。これにより、パレスチナを承認した国は約一六〇カ国、国連加盟国の八割を超える規模となった。国連人権理事会の独立調査委員会が、ガザでのイスラエル軍による攻撃を「ジェノサイド」と認定した直後のことである。国際世論が、ガザでの惨禍を座視せず、二国家共存の道筋を改めて確認しようとする意志を示した象徴的な一歩であった。
だが日本政府は今回の承認に踏み切らなかった。岩屋毅外相は「イスラエルの姿勢を硬化させかねない」と理由を述べ、国家承認を先送りした。この判断は昨年四月、日本が安保理に提出されたパレスチナの国連加盟を支持した行動と明らかに矛盾する。国際社会の大勢と逆行する姿勢は、アラブ・イスラム諸国の信頼を損ない、日本の中東外交の根幹を揺るがしかねない。戦後一貫して「平和国家」を掲げてきた日本が、この時代にあってなぜ躊躇するのか。深い問いが突きつけられている。
ガザの現実は想像を絶する。地上侵攻による住民の犠牲は六万五千人を超え、物資の搬入制限で飢餓が広がり、四百三十人以上が栄養失調で命を落とした。爆撃で倒壊した家屋の下に、家族を探し続ける人々の姿が報じられる。ある母親は「子どもの泣き声が聞こえた気がして瓦礫を掘り続けたが、見つかったのは小さな靴だけだった」と語った。人間の尊厳がこのように踏みにじられる現実に、国際社会はどう応えるのか。日本はその責任を免れない。
イスラエル国内でも、ネタニヤフ政権の強硬策に異論が噴出している。治安機関や軍の一部は、長期的な安全保障をむしろ危うくするとの警鐘を鳴らす。それでも極右勢力と結託した政権は戦闘を継続し、政治的延命を図っている。こうした姿勢に対して、世界の諸国が「国家承認」という形で明確な意思を示すのは当然である。承認は単なる外交儀礼ではなく、イスラエルの占領と併合を拒み、平和共存の未来を選び取る行為なのだ。
ここで私たちは、聖書の言葉を思い起こす。「平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ五・九)。平和を実現するとは、単に争いを避けることではない。権力による抑圧や不正義をただす勇気を持ち、苦しむ隣人の声に耳を傾けることである。イスラエルとパレスチナの人々が共に生きる未来を実現するために、国際社会が果たすべき責任は明白だ。日本はその責任から逃れてはならない。
戦後日本は、七三年の第四次中東戦争のさなか、イスラエルに占領地からの即時撤退を求める官房長官談話を発表した歴史を持つ。エネルギー危機に直面しつつも、国際法に基づく公正な立場を貫こうとした。その歩みを思えば、今回の承認先送りは過去の積み重ねを自ら崩すものである。米国の拒否権を恐れ、同盟関係への「忖度」を優先するなら、日本は平和主義の旗を自ら降ろすことになるだろう。
もちろん、日本が独自に国家承認を行っても、直ちに現実が変わるわけではない。イスラエルの政策を転換させる力は限られている。それでも、声を上げることには意味がある。国際社会の多数派に加わり「二国家共存こそ唯一の道だ」と明確に意思表示することは、暴力の連鎖を断ち切るための一歩である。黙して語らず、傍観することこそが最大の加担であることを、私たちは忘れてはならない。
日本の教会にとっても、これは遠い世界の話ではない。福音は「平和を告げる良い知らせ」として、民族や国境を越える。教会がパレスチナの人々と共に祈り、平和を求める声をあげることは、単なる政治的立場表明ではなく、信仰の応答である。私自身、数年前にヨルダン川西岸で出会った青年の言葉を忘れられない。「私たちは石を投げたいのではなく、学びたい、働きたい、家族と暮らしたいのです」。その切実な願いを思うとき、日本の沈黙はあまりに重い。
「あなたがたは、もはや外国人でも寄留者でもない。聖なる者たちと同じ国民であり、神の家族なのである」(エフェソ二・一九)。この言葉は、民族や国境の壁を超えた共生のビジョンを示している。パレスチナの人々の苦悩を他人事とせず、共に担うこと。それが、神の家族に連なる者の責務である。国家承認は、その具体的な一歩であり、国際社会の倫理的責任の象徴なのである。
日本政府に求められるのは、同盟国の顔色をうかがう外交ではなく、憲法に刻まれた平和主義の精神に立脚した決断である。イスラエルに対してもパレスチナに対しても、公正な声を発し続けることこそが、日本の国益を守り、国際社会での信頼を確かなものにする。ガザの子どもたちの命を前に、私たちは問われている。「あなたはこの惨状を見てなお沈黙を選ぶのか」と。
国家承認をめぐる判断は、単なる外交案件にとどまらない。人間の尊厳と平和を守るために、今を生きる私たちがどのような声を発するかが問われている。日本が再び、真に平和国家としての矜持を示す日を、世界は待っている。
二.キャンセルカルチャーの過激化と対話の可能性
アメリカで生まれた「キャンセルカルチャー」という現象は、いまや世界を揺るがす社会的潮流となっている。もともと不祥事を起こした人物や差別的な言動をした団体に対し、消費者や市民が抗議し、不買や不支持を通して責任を問うという、市民的抵抗の一形態だった。だが近年、その動きは過激さを増し、個人や集団を社会から排斥する「公開処刑」に似た様相を呈し始めている。
象徴的だったのは、米保守系インフルエンサー、チャーリー・カーク氏が演説中に銃撃され命を落とした事件である。この悲劇そのものが衝撃的であったにもかかわらず、SNS上ではリベラル派の一部利用者が「溜飲が下がる」といった書き込みを行い、その結果として職場を追われる事例が相次いだ。暴力に対する言葉が、別の暴力的排除を招くという、暗い連鎖を目の当たりにしたと言わざるを得ない。
こうした事例は、米国に限らない。日本でも、過去の発言や表現が「不適切」と糾弾され、芸術家や音楽家が活動の場を失う例が繰り返されてきた。二〇二四年には人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」が発表した楽曲「コロンブス」が、植民地支配を連想させるとして謝罪に追い込まれた。さらに宝塚歌劇団が舞台で「海ゆかば」を用いたことが、戦時中の利用を理由に批判を受け、上演から外されたことも記憶に新しい。歴史や文化の評価は一義的に定まるものではないにもかかわらず、特定の文脈だけを取り出して糾弾し、排除にまで至る現象は、自由な議論を委縮させる危うさをはらんでいる。
オバマ元大統領はかつて「素晴らしいことをした人にも欠陥はある」と繰り返し述べた。人間の営みは常に不完全であり、過去の時代状況の中で行われた言動を、現代の価値基準だけで裁くことには限界がある。にもかかわらず、キャンセルカルチャーの過激な運動は、法の原則さえ飛び越え、「罪刑法定主義」や「法の不遡及」といった根本的理念を無視している。かつての少年時代の行為や、数百年前の歴史的人物の行動を引きずり出して糾弾することは、もはや正義の名を借りた断罪に近い。
ここで私たちが立ち止まって考えたいのは、「正義」とは何か、という問いである。旧約聖書の伝道の書には「人はみな罪を犯していない者はいない」と記されている。欠けを持たない人間はいない。ゆえに、他者の過去の過ちを暴き立てるとき、同時に自らの不完全さも問い返されるはずである。それを忘れたとき、正義は容易に残酷さへと転じる。
他方で、キャンセルカルチャーが生まれた背景には、現実の差別や暴力、構造的不正義があることも直視しなければならない。声を上げなければ変わらない社会の中で、市民が連帯して企業や権力者に圧力をかけたことが、一定の成果をもたらしてきたことも事実である。#MeToo運動が明らかにした性暴力の実態は、まさにキャンセルカルチャー的な告発がなければ闇に葬られていたかもしれない。つまり問題は「声を上げること」そのものではなく、その方法と目的がどこへ向かうかにある。
聖書は「互いに忍び合い、もし互いに責めることがあっても赦し合いなさい」(コロサイ三・一三)と勧める。赦しは過去をなかったことにするのではない。過ちを認めつつ、それを超えて共に生きる道を模索することである。キャンセルの名のもとに他者を排除し尽くすのではなく、対話と修復を通して関係を築き直すことこそ、真の正義に近づく道であろう。
「敵を愛しなさい」とのイエスの言葉は、現代のキャンセルカルチャーのただ中でこそ響く。相手を排除するのではなく、対話の場に招き入れること。誤りを犯した者に責任を求めつつも、人としての尊厳を奪わないこと。その姿勢がなければ、社会は分断を深め、相互不信に沈むばかりである。
日本社会にも同様の課題がある。SNSでの炎上や集団的糾弾は、匿名性に守られた残酷さを帯びやすい。言葉の暴力が命を奪った例も少なくない。だが、私たちには別の道が開かれている。互いの違いを尊重し、議論の余地を残し、赦しと修復を選び取る道である。これは単なる倫理の問題ではなく、信仰共同体にとっては福音に根ざした使命でもある。
キャンセルカルチャーの過激化に直面するいま、私たちは「断罪」か「赦し」かの二者択一ではなく、責任と対話を両立させる道を歩まなければならない。正義を掲げつつも、人を生かす正義を選び取ること――それが、神の国を証しする共同体の使命である。
三.性同一性障害特例法・外観要件違憲判決と人権の行方
札幌家裁が、性同一性障害特例法に定められた「外観要件」を違憲と判断した。性別変更を望む人が、性器の外観を変える手術やホルモン投与を受けなければならないとする規定は、憲法一三条の「個人の尊重」に反するとして無効としたのである。これは初めて外観要件を正面から違憲と断じた司法判断であり、日本の人権保障の歴史に新たな一頁を開くものとなった。
特例法は二〇〇三年に施行され、性別変更には五つの要件を設けた。二〇二三年、最高裁大法廷は生殖不能要件を違憲と判断している。今回の外観要件違憲判断によって、残された要件の妥当性にも改めて疑問が突きつけられている。性別変更を求める人々に、身体的に重大な侵襲を強いることが、果たして正義といえるのか。その問いは、単に法律技術的な問題にとどまらず、人間の尊厳そのものに関わっている。
外観要件の目的は、公衆浴場やトイレの利用に混乱を生じさせないためとされてきた。しかし、札幌家裁は「多くの当事者はそもそも利用を控えている」と指摘した。つまり立法が想定した「混乱回避」は現実と乖離していたのである。判決はさらに、ホルモン療法や外科手術に伴う健康リスク、費用負担の大きさを挙げ、国家が個人に強制することの不合理を明確にした。医学的知見が進むなかで、身体的治療を受けなければ「自分らしい性」を生きられないという発想自体がすでに時代遅れとなっている。
それでもネット上では「女性の安心が脅かされる」「社会が混乱する」といった懸念が繰り返される。こうした声は根強い偏見を映し出すものである。だが、差別や恐怖を煽る言説に立法が迎合するなら、当事者の尊厳は永遠に犠牲にされるだろう。むしろ社会に必要なのは、対立を煽るのではなく、冷静な合意形成と多様性を受け入れるための工夫である。例えば公衆浴場の時間帯貸し切りや、施設ごとのルールづくりなど、すでに実践されている取り組みを広げることができる。
ここで私たちは聖書の一言を思い起こす。「人は皆、神のかたちに造られた」(創世記一・二七)。性のあり方が多様であるとしても、一人ひとりが神のかたちを宿す存在であることに変わりはない。だからこそ、社会の制度がその多様性を否定し、特定の身体的形態を強制するなら、それは神の創造をゆがめる行為にほかならない。人間を「あるべき形」に押し込めることは、神の自由なわざを制限することにつながる。
国会は長らく特例法の改正を先送りしてきた。しかし最高裁と家裁の連続する違憲判断は、もはや猶予が許されないことを示している。立法府が手をこまねけば、司法判断と現実との乖離が拡大し、当事者はさらなる苦しみに追いやられる。いま求められているのは、性の多様性を正面から認め、誰もが「自分らしく」生きられる制度を整えることだ。
もちろん、社会の不安や戸惑いを軽視することはできない。だが、その不安は偏見や無理解から生まれるものであり、時間をかけた教育と対話によって解消していくしかない。教会はその過程において重要な役割を果たすことができる。信仰共同体が率先して性的少数者を受け入れ、共に祈り、共に生きる姿を示すとき、社会は変わる。キリストが差別された人々に近づき、彼らの尊厳を回復したように、教会もまた「隣人」として寄り添う使命を担っている。
「あなたがたはもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な者もなく、男と女もない。あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからである」(ガラテヤ三・二八)。この言葉は、性の多様性を受け入れる社会のビジョンを先取りしている。人間の区別や壁を超えて、一人ひとりを尊重する共同体。それこそが教会の原点であり、社会が目指すべき方向性である。
札幌家裁の判断は、制度の不備を突いた司法の声であると同時に、社会全体への問いかけでもある。私たちはどのような社会を築きたいのか。恐怖と偏見に基づく閉ざされた社会か、それとも多様性を認め合う開かれた社会か。その選択が、未来の世代の生き方を決定づける。人権の保障は、時代に応じて拡張され続けるべきものだ。いま、その拡張の責任が私たちに託されている。
結語 いのちの声に応える責任
この一か月の報道を振り返るとき、胸の奥に重く沈むのは、人間の尊厳が繰り返し試されているという事実である。ガザの瓦礫の下から助けを求める子どもの声。SNSで断罪され、居場所を失った人の沈黙。自らの性を偽らざるを得なかった当事者の苦悩。それぞれの出来事は遠く離れているようで、実は同じ問いを私たちに突きつけている。――あなたは、この声を聞いてなお、沈黙を選ぶのか。
パレスチナの惨禍を前にして、日本政府は国家承認を先送りした。だが「二国家共存」こそ唯一の平和への道だと訴える国際社会の大勢は、すでに明らかである。声を上げることは、すぐに現実を変える力を持たないかもしれない。しかし、語らぬことは加担に等しい。戦後日本が掲げてきた平和主義を、同盟国への「忖度」によって曖昧にしてはならない。ここで問われているのは、外交の巧拙ではなく、人間の命を重んじるという基本的な倫理の選択である。
キャンセルカルチャーの過激化もまた、私たちに同じ問いを返している。誰もが過ちを犯し、欠けを抱えて生きている。誤りをただすことと、人格を否定し社会から排除することは、本来別の次元であるはずだ。にもかかわらず、正義の名の下に人を断罪する風潮が強まるとき、そこには冷酷さが潜んでいる。赦しや回復の余地を閉ざした社会は、やがて自らをも傷つけるだろう。必要なのは、責任を問いつつも関係を立て直す「修復の正義」である。イエスが示された赦しの道は、現代社会の分断を乗り越えるための指針となり得る。
札幌家裁の違憲判断は、性的少数者の声に光を当てた。性別を変更するために身体を傷つけることを強いる法律は、もはや人間の尊厳を守る法ではない。判決は、社会が抱く不安や偏見をそのまま法律に刻み込むのではなく、一人ひとりが自分らしく生きる権利を保障するよう求めている。性の多様性を受け入れることは、伝統を壊すことではなく、神が造られた多様な命を尊ぶことにほかならない。ここでも、問われているのは私たちがどのような社会を選び取るのか、という根本的な姿勢である。
三つの出来事を結ぶのは「声なき声にどう応えるか」という一点である。ガザで命を奪われた人々の声。断罪のただ中で孤立する人の声。性のあり方を理由に生きづらさを抱える人の声。それらは、聞こえにくいが確かに存在する。社会の雑踏や政治の駆け引きの陰にかき消されがちなその声にこそ、神の呼びかけが宿っている。私たちが耳を澄まし、応答することを求めている。
聖書は「真理はあなたがたを自由にする」と語る(ヨハネ八・三二)。真理とは、力を持つ者が都合よく語る物語ではない。むしろ、犠牲にされた者や沈黙を強いられた者の側に立ち、その現実を直視する勇気である。自由とは、他者を排除する力ではなく、共に生きる道を選び取る力である。その真理に生きるとき、私たちは初めて平和の共同体を形づくることができる。
もちろん、その歩みは容易ではない。外交の現場では利害が絡み合い、社会の議論は感情的に分断され、制度改革には時間がかかる。それでも、教会が福音の光を証しするとは、まさにその困難のただ中で「いのちを軽んじてはならない」と告げ続けることにある。祈りは現実逃避ではなく、現実を変えるための第一歩である。祈りと共に声を上げ、行動を起こすとき、希望は確かに芽生える。
未来の世代へ、私たちが渡すべきものは何か。それは沈黙でも、忘却でもない。痛みに向き合う勇気と、和解を選び取る誠実さである。いのちの声に応える責任を果たすとき、教会はただの宗教団体ではなく、世界における和解と共生の証人となるだろう。その道を共に歩み続けたい。