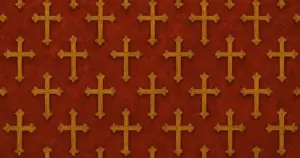信仰と政治の境界を問う ― 日本イスラエル・クリスチャン交流会と倫理の課題

佐藤俊介(自由と友愛の独立アングリカン教会 大主教)
9月16日、「日本イスラエル・クリスチャン交流会」(英語名:Japanese Parliamentary Israel Allies Caucus)が参議院議員会館で発足(再始動)しました。駐日米国大使ジョージ・グラス、駐日イスラエル大使ギラッド・コーヘン、イスラエル同盟財団(IAF)会長ジョシュ・ラインスタインらが出席し、日本側は金子道仁参議院議員(牧師)らが顔をそろえました。公式報道や当事者の発信でも確認できます。
(IAFは各国議会に親イスラエル議連を組織し「信仰に基づく外交」を推進、現在「6大陸62カ国」にネットワークがあると説明しています。)
当日の説明では、ガザでの配食を担う米主導の「ガザ人道財団(GHF)」の活動が強調されましたが、国連機関・関係者からは同スキームの中立性や安全面への懸念が公表されています(UNRWAトップの批判など)。一方でGHF側は批判を「誤情報」として否定し、中立性を掲げています。ここは評価が割れている論点で、私たちは“人道原則の非軍事性・中立性・ニーズ基準”が実地で担保されているかを継続監視すべきです。
同会発足の顔触れには、日本会議の新会長・谷口智彦氏や「救う会」の西岡力氏ら、日本の右派世論形成に強い影響力を持つ面々も名を連ねました。日本会議は今年7月に谷口氏が会長就任を公表、憲法改正や皇位継承をめぐる積極的発信を続けています。宗教右派と国家主義的アジェンダの接合点がどこに置かれているのか、透明性と説明責任を私たちキリスト者が求めるべき理由がここにあります。
さらに政治文脈です。日本政府は9月、パレスチナ国家承認の「見送り」を事実上確認しました。米国との関係や情勢判断が背景にあるとの報道です。しかし、まさにこの時期に「親イスラエル・信仰外交」の国内窓口が成立(再始動)したことは、偶然とは言い難いタイムラインです。ここでは、特定国家への過度の同調(対米配慮を含む)が、結果として福音の倫理――弱者保護・和解・正義――を後景化させていないかを自戒したい。
私たちは、イスラエルを「聖書の物語の舞台」として愛することと、現政権(たとえばネタニヤフ政権)の政策を白紙委任することを混同してはなりません。教会は国家の道具ではなく、主イエスに従う民です。ゆえに、①人道支援の実効性と中立性の検証、②ロビー活動の資金・人的流れと意思決定経路の公開、③教会が政治連携に与する際の神学的基準(平和・正義・弱者保護・隣人愛)の明示――これら最低限の説明責任を、当該ネットワークに強く求めます。IAFが誇る「信仰に基づく外交」が、弱者のいのちを守るための“福音に基づく倫理”と一致しているのか、吟味が不可欠です。
ここで私たちが問うべきは、日本のキリスト教関係者が、いかにして「倫理的整合性」を保ち得るかです。旧統一協会が長年、宗教の名を用いて政治や経済に影響を及ぼし、信徒の人生を翻弄してきたことは記憶に新しい。その反省を共有するはずの私たちが、今度は「親イスラエル」という旗の下で、再び政治権力と癒着し、信仰を利用する構造に陥る危うさはないのか。人道や聖書的価値の言葉が、実際には国際政治の取引に奉仕してしまうなら、それは同じ轍を踏むことに他ならないのです。日本のキリスト教界の指導者や牧師、研究者、そして議員らは、旧統一協会問題を批判してきたその言葉を、自らに突き付けねばなりません。
最後に、読者の友へ。イスラエル支持か否かという二分法ではなく、「権力と結びつく宗教」がいつでも堕落し得るという聖書的警告(王と預言者の緊張関係)を思い起こしましょう。国家・政権・ロビーのいずれにも過度に与しない――それが“主を第一”とする信仰の実践です。日本の教会が、右派的“へそ曲がり”の自己目的化に流されず、パレスチナの人々も含むすべての隣人のいのちと尊厳を等しく守る声であるために。