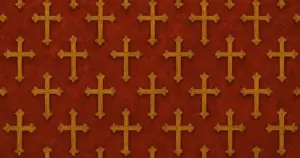信教の自由を楯にする危うさ ― SALTY の論陣の裏側を問う

佐藤俊介(自由と友愛の独立アングリカン教会 大主教)
SALTY(日本キリスト者オピニオンサイト)が8月11日、お茶の水クリスチャンセンターで「信教の自由を脅かす解散命令」を掲げた集会を開いた。登壇者は西岡力氏ほか。主催者の公式報告や公式YouTubeの動画が残っている。そこで語られた主張の骨子は、旧統一協会(世界平和統一家庭連合)への解散命令は宗教の自由への国家介入であり、手続も不透明だ、というものだ。だが、そこには決定的に欠けている前提がある。東京地裁は2025年3月25日、同教団に「解散を命じる」決定を出し、長年にわたる組織的・全国的・悪質な勧誘行為による甚大な被害を事実として認定している。解散命令は抽象的な価値判断ではない。具体的な被害と法的根拠に基づく司法判断だ。
生の数字を直視したい。文科省は解散請求時点で、民事訴訟で不法行為が認められた判決32件、被害者169人、認容額約22億円、和解等を含めれば約1,550人・約204億円と説明した。家族関係の破壊や精神的損害まで含めれば、金額に現れない被害はさらに大きい。最高裁は2025年3月3日、「刑事法違反に限らず民法上の不法行為も解散命令事由となり得る」と明示し、地裁決定の前提を固めている。つまり本件は“信教の自由”と“恣意的国家介入”の対立ではない。長期・組織的な違法・有害行為に対する司法の応答である。
ここで、SALTYの主筆、西岡氏の「素性」と論調の文脈も押さえておく必要がある。同氏は長年、北朝鮮による拉致被害者支援運動の中心人物として活動し、安倍晋三氏と“共に歩んだ”と自ら回想している。安倍氏の政策ブレーンの一人と報じられた経緯もある(本人は「ブレーンではない」と否定)。また、同氏は『安倍晋三の歴史戦』など保守論壇で一貫した立場をとり、慰安婦問題をめぐって被害証言の信用性を強く疑う論陣も張ってきた。こうした“被害の縮小・相対化”に傾く論法が、旧統一協会問題においても「宗教の自由」の名で被害者の実相を後景化させる方向に作用していないか。少なくとも、読者が文脈を知らないまま耳当たりのよいスローガンに説得される危険は高い。
安倍氏と旧統一協会(および関連団体UPF)をめぐる客観的事実も記録しておきたい。2021年9月、安倍氏はUPFの国際イベントにビデオメッセージを寄せ、敬意や評価の言葉を述べたことが主要メディアで報じられている。また、自民党は党内調査で相当数の国会議員に教団との関係があったと公表し、党執行部の人事や方針を見直した経緯がある。事件後の世論動向も含め、政治と教団の関係の広がりは、もはや否定のしようがない。ゆえに、教団への司法判断を「宗教弾圧」と単純化することは、政治的現実の一部を切り落とす“説明の省略”である。
法の枠組みを確認する。宗教法人が公益を標榜しながら、組織として多数者の生活・財産・心身に重大な侵害を与えた場合、宗教法人法81条に基づく解散命令は、憲法上の「信教の自由」を踏まえたうえでなお許容される例外措置である。今回、文化庁は長年の被害の組織性・悪質性・広域性を具体的資料で示し、地裁はそれを踏まえて決定した。司法プロセスは公開され、上級審のチェックも働く。ここに「密室の国家弾圧」を読み込むのは、読者をいたずらに煽るレトリックにすぎない。
では、キリスト者はどう応じるべきか。第一に、自由は責任によって鍛えられるという単純にして重い原則を取り戻すことだ。教会は公的領域に対して批判的距離を保つと同時に、被害者に寄り添う倫理的責任を負う。今回の争点で言えば、国家の越権を警戒する姿勢は維持しつつも、被害者の救済と再発防止を最優先に置くことが、公同の教会の証しに適う。第二に、事実を起点に語ることだ。数字と判決理由、公式記録を丹念に読む。先入観と政治的帰属意識をいったん脇に置く。それは信仰の弱さではない。むしろ真理への忠実である。
最後に、SALTYの右派シンパにも苦言を呈する。右翼志向で胸を張るのもご自由に、と言っておこう。しかし、その旗の下で、長年苦しめられてきた人々の痛みや、家族が壊れていった現実を軽く扱ってはならない。国家の恣意に抗するためには、教会の側もまた透明性と説明責任を自らに課す必要がある。私たちが守るべきは、特定団体の既得権ではない。自由の名において隣人の尊厳を踏みにじる構造から、人を解き放つことである。右派的なへそ曲がりもいい加減、やめるべきだ。それが、公共に向き合うキリスト者のまっとうな流儀である。
――
(主要出典:SALTY公式告知・動画、東京地裁決定報道、文科省会見記録、最高裁判断報道、自民党と教団の関係に関する調査・報道、西岡氏の経歴・著作情報など。)