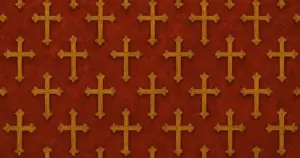聖霊降臨後 第十五主日 説教草稿「神に仕える自由 ― 富と祈りの間で問われる忠実さ」

【教会暦】
聖霊降臨後 第十五主日(特定二十) 二〇二五年九月二十一日
【聖書箇所】
旧約日課 :アモス書 八章四〜七節(八〜一二節)
使徒書 :テモテへの手紙一 二章一〜八節
福音書 :ルカによる福音書 十六章一〜一三節
【本文】
はじめに 富と祈りのはざまで生きる
九月も下旬を迎え、空はすでに秋の澄んだ色合いを帯びている。日中はなお夏の名残の暑さがあるものの、朝夕の空気には確かな涼しさが宿り、虫の声が夜ごとに重なり合っている。日本列島各地では台風や豪雨による被害の報道が絶えず、自然の恵みと脅威が同居する季節を私たちは生きている。そのただ中で、教会暦は「聖霊降臨後第十五主日」を迎えた。主日の聖書日課は、アモス書、テモテへの手紙、ルカによる福音書を通して、富と祈り、そして信仰の忠実さをめぐる問いを私たちに突きつけている。
旧約の日課であるアモス書は、社会的不正と弱者の切り捨てを告発する。秤をごまかし、貧しい人を履物一足で買い取るという言葉は、当時の社会がいかに弱者を軽視していたかを映し出す。しかしそれは過去の話ではなく、今日の格差社会にも重なる現実である。経済成長の数字が語られる一方で、生活に苦しむ人々が声を上げられない状況があるとき、アモスの預言は私たち自身に突き刺さる。
使徒書の日課である一テモテ書は、「すべての人のために祈れ」と勧める。為政者を含め、社会を導く者たちを神の御前に置き直す祈りは、権力に迎合することではなく、むしろ権力の偶像化を防ぐための営みである。教会の祈りは内向きではなく、公共的な責任を担う行為であることをパウロは告げている。
そして福音書の日課は、難解で知られる「不正な管理人の譬え」を示す。富を浪費した管理人が、債務者の負債を減じて友を得ようとする。その狡猾さに対して主人は彼を褒めた。イエスはこの行為を不正そのものとしてではなく、富にしがみつかず関係性に活路を見いだした点に注目せよと語る。そして「あなたがたは神と富とに仕えることはできない」と結ばれる。これは信仰の核心を突く言葉であり、私たちの生き方を根底から問う。
本主日の聖書日課を貫くのは、「富の絶対化に抗い、神に仕える自由を選び取れ」という呼びかけである。社会的不正を告発し、すべての人のために祈り、日常の小さな忠実さを積み重ねること。そこに神の国の希望が現れる。私たちは富と祈りのはざまで揺れる存在だが、その選択の一つひとつが永遠の住まいにつながっていく。本日の礼拝で与えられる御言葉を通して、私たちは再び問いかけられている――「あなたは誰に仕えるのか」と。
Ⅰ節 不正の秤と神の沈黙の危機
秋分が近づき、朝夕の空気はようやく涼しさを帯び始めている。稲刈り前の田畑には黄金の穂が揺れ、実りの季節を迎えているが、台風や豪雨の被害を受けた地域の報道も相次いでいる。自然の恵みと同時に災厄をもたらす現実の前で、私たちは人間の無力を痛感する。こうした現実を見つめながら本日の聖書日課を読むとき、預言者アモスの鋭い言葉が耳を刺す。「弱い者を踏みにじり、貧しい人を押しつぶす者よ。…正しい秤を偽り、銀で貧しい者を買い取り、履き物一足で乏しい者を買い取る」(アモス8:4-6)。ここには、豊作の喜びの陰で貧者が犠牲となり、不正な商取引によって命さえも安売りされる現実が描かれている。
アモスが活動した紀元前8世紀のイスラエルは、一見すると繁栄を誇る時代であった。北王国は経済的な成長を遂げ、商業活動も盛んであったと伝えられる。しかし、その繁栄の陰には、社会的不公正の拡大と、弱者の切り捨てが横行していた。安価な履物一足で人の命を買うという表現は、当時の貧困層の立場がいかに無力であったかを示している。アモスは宗教儀礼の盛大さや政治的安定の中に隠された不義を見抜き、神の怒りを宣告した。「主なる神は誓って言われる。私は彼らの行いを決して忘れない」(同8:7)。この言葉は、歴史を越えて私たちの社会をも照らし出す。
現代の日本社会に目を向けるとき、アモスの預言は決して遠い世界の話ではない。近年、生活保護の受給者や年金制度からこぼれ落ちる人々、労働環境の不安定化による「ワーキングプア」、さらには難民や外国人労働者に対する冷たいまなざしなど、弱い立場に置かれた人々が日常的に搾取や無視にさらされている現実がある。経済統計上の回復や株価の上昇が語られる一方で、日々の生活に追われる家庭は増え続けている。繁栄の数字と生活の実感が乖離する社会は、アモスが告発した時代と重なる部分が多いと言わざるを得ない。
さらに今日の聖書箇所には、不気味な警告が続く。「見よ、その日が来る、と主なる神は言われる。その日、私はこの地に飢えを送る。パンの飢えではなく、水の渇きでもない。主の言葉を聞くことの飢えである」(8:11)。物質的な飢饉よりも深刻なのは、神の言葉が聞こえなくなるという霊的飢饉である。社会の不正と搾取が進むとき、人々は良心の声を聞き取る力を失い、やがて神の沈黙が訪れる。その沈黙は、人間が自らの耳を塞ぎ、神の正義を拒んだ結果としてもたらされる。
この「神の沈黙の危機」は、現代社会においても現実的な課題である。デジタル化と情報化が進み、日々膨大なニュースや言葉が飛び交う一方で、人々の心は逆に空洞化し、真実の言葉が届きにくくなっている。効率や利益を優先する経済論理が社会全体を支配するとき、弱者の声は「聞くに値しない雑音」とされ、かき消されていく。そこに神の言葉を聞くことの飢えが生まれる。表面的には情報があふれていても、真理を告げる言葉に飢えるという逆説的な現象が広がっているのではないだろうか。
アモスの預言を受け止めるとき、教会は自らに問いを突きつけられる。私たちは弱者の叫びを聞き取ろうとしているか。あるいは、繁栄の物語に酔い、耳に心地よい言葉だけを求めていないか。もし教会が神の言葉を曖昧にし、社会的不正に沈黙するならば、アモスが告げた霊的飢饉は教会自身をも覆うであろう。神の言葉が聞こえなくなること、それこそが最大の危機である。だからこそ、預言者は繰り返し告げる。「主の言葉を聞け」と。
秋の実りを迎えるこの季節に、私たちは社会の片隅で声を上げることさえできない人々を思い起こすべきである。その声を無視する社会は、やがて自らも神の沈黙に包まれる。しかし、もし私たちがその声を神の言葉として聴き取るなら、そこにこそ新しい希望の芽が生まれるのではないか。
Ⅱ節 祈りの共同体と公正の責任
使徒書の日課は「すべての人のために願い、祈り、とりなし、感謝をささげなさい」(一テモテ2:1)と始まる。パウロが若い指導者テモテに与えたこの勧告は、教会の本質を示す。祈りは単なる個人的営みではなく、共同体の公的責務である。特に「王とすべて高い地位にある人のために」(2:2)祈れという言葉は、権力者の善悪を問わずに祈りの対象とすることを求めている。それは権力に迎合することではなく、むしろ権力者が神の義のもとに裁かれる存在であることを祈りによって確認する行為である。
アモスが告発した不正の秤は、支配層や商人たちの手に握られていた。テモテ書簡が求める祈りは、そうした力ある者を神の御前に置き直す営みである。教会が権力の不正に沈黙すれば、やがて共同体全体がその罪に巻き込まれる。だからこそ祈りは、権力者を批判しつつも同時に彼らのためにとりなしを行うという、二重の責任を担うのである。これは単なる敬虔の姿勢ではなく、きわめて政治的かつ公共的な実践である。
現代の社会状況を見れば、この勧告の意義は一層重みを増している。世界各地で戦争や紛争が絶えず、国際秩序は大きく揺らいでいる。日本もまた、安全保障や経済政策をめぐる緊張の中に置かれ、政治の決断が国民生活を直撃する時代にある。こうした状況で、教会が為政者のために祈ることは、彼らの決断が正義と平和にかなうものとなるよう願う行為である。それは単なる「国の安泰」を願う祈りではなく、弱者を犠牲にしない政策が実現するようにとりなす祈りである。
ここで重要なのは、パウロが「すべての人のために」と強調している点である。祈りの対象は、特定の民族や階層に限られない。社会的に見過ごされる人々、声を上げられない人々もまた、その範囲に含まれる。祈りが共同体の壁を越えて広がるとき、教会は自らの殻を破り、普遍的な公正の担い手となる。換言すれば、祈りは「弱者を思い出す」行為であり、社会の中で忘れられた者を再び神の御前に呼び戻す営みである。
今日、難民や移民労働者、社会的少数者に対する排斥的言説が広がる中で、教会が「すべての人」のために祈ることは極めて預言的な行為である。私たちが意識的に彼らの名を祈りに含めるとき、社会の無関心と排除に抗う小さな抵抗が生まれる。祈りは静かな行為に見えて、実は社会を揺り動かす力を秘めている。アモスが語った「神の沈黙」に抗する道は、まさに祈りによって開かれるのではないか。
さらに、パウロは「清く、敬虔に落ち着いた生活を送るため」(2:2)と祈りの目的を述べる。ここでいう「落ち着き」は、無関心な安逸ではなく、義と平和に根ざした安定を意味する。社会が不正と暴力に覆われるとき、人々は恐怖と不安に支配される。祈りはその中で神の平和を呼び込み、共同体に確かな軸を与える。つまり祈りは単なる言葉の積み重ねではなく、信仰共同体の存在意義そのものを形づくる営みである。
この点で、教会の祈りは社会運動や政策提言と切り離されたものではない。祈りは現実逃避ではなく、現実に対する信仰的応答である。弱者の叫びを思い起こし、権力者の決断を神の御前に置き直すこと。そこにこそ、教会の祈りの公共性がある。もし祈りが共同体の内側に閉じられ、外の世界に触れないなら、それはアモスが告発した虚しい祭儀と変わらないだろう。祈りは神に届くと同時に、社会の現実を変えるために私たち自身を動かす力となるのである。
Ⅲ節 不正な管理人の譬えと信仰の試金石
ルカによる福音書16章は、一見すると解釈に難しい譬えを私たちに提示する。主人の財産を浪費した不正な管理人が、解任を告げられる。彼は自分の将来を案じ、主人の債務者たちの負債を勝手に減らし、恩を売る。その狡猾さに対して、主人は彼を褒めるのである(16:8)。一体、なぜ不正が称賛されるのか。この箇所は古代から多くの注解者を悩ませてきた。
注目すべきは、イエスがここで「この世の子らは、自分の仲間に対して、光の子らよりも抜け目なくふるまっている」(同)と言われた点である。不正そのものを是認しているのではない。むしろ、危機に直面したときの判断力と先見性に注目せよと促しているのだ。管理人は、財産を私物化することをやめ、関係性を築くことに活路を見いだした。彼にとって財産はもはや絶対ではなく、人との絆を生き延びるための手段と化した。この転換が、信仰の視点から重要である。
イエスは続けて語る。「不正の富で友を作りなさい。そうすれば、富がなくなったとき、あなたがたは永遠の住まいに迎え入れてもらえる」(16:9)。ここで「不正の富」と呼ばれるのは、地上の富が常に不完全であり、しばしば不公正の中で成り立っているという現実を指している。富そのものが悪ではないが、人間の社会においては必ずしも正義にかなって用いられてはいない。だからこそ、その限界を自覚しつつ、富を用いて隣人との関わりを築けと命じられる。これは富を神とする偶像礼拝に陥るなという警告であり、同時に、富を通して真の交わりを形成せよという挑戦でもある。
この譬えを現代社会に引き寄せるならば、経済活動の中で避けがたく不正や矛盾に直面する私たちの立場が映し出される。私たちは、完全に透明で正しい富だけを用いることはほとんどできない。製品やサービスの背後には、環境破壊や低賃金労働などの問題が潜んでいる。私たちの消費や投資は、知らず知らずのうちに不正の構造に関わってしまう。だからこそ重要なのは、富の純粋性ではなく、それをどのように用いるかである。もし富を自己の欲望や安逸のためだけに費やすなら、私たちは不正の連鎖を深める。しかし、富を人と人との関係、隣人の支援、共同体の再建のために用いるならば、そこに神の国のしるしが現れる。
イエスの言葉はさらに核心に迫る。「小さなことに忠実な者は、大きなことにも忠実である。不正な富に忠実でなかったら、だれがあなたがたに本当の富を任せるだろうか」(16:10-11)。ここで問われているのは、富の規模ではなく、忠実さの質である。日常の小さな選択において、私たちは常に神と富との間で試されている。安易な妥協、不正の黙認、弱者の無視。そうした「小さな不忠実」が積み重なるとき、信仰は空洞化する。逆に、小さな場面であっても誠実に隣人のために用いるならば、その姿勢は神に認められ、より大きな使命を託される。
最後にイエスは断言する。「あなたがたは神と富とに仕えることはできない」(16:13)。富はしばしば人間の心を支配し、神の座を奪う。だからこそ富に対する態度は、信仰の試金石となる。私たちは富を絶対化する社会の中で、あえて神を選ぶ勇気を求められている。富を神とする世界にあって、神を選ぶことは時に不利益を伴い、分裂を生む。しかしその選択こそが、光の子としての道なのである。
この譬えは、現代社会の倫理的ジレンマに直結している。私たちは完全に清い富を持つことはできないが、その現実の中でどのように忠実に生きるかが問われている。不正の富を用いて隣人とつながり、神に仕えることを選ぶ。そこに信仰の真価が現れる。
Ⅳ節 富と偶像礼拝を超える共同体の道
アモスが告発した不正、パウロが示した祈りの公共性、イエスが語った不正な管理人の譬え――これらを重ね合わせるとき、浮かび上がるのは「富と権力が神の座を奪う危険性」である。人間は目に見えるものに依存しやすく、富を持つ者が力を握り、やがてそれが偶像化される。歴史を振り返れば、帝国も国家も富を基盤に栄え、同時に富をめぐる争いによって滅びてきた。偶像礼拝の根底には常に「富への過信」がある。
ルカ福音書の終わりの言葉――「神と富とに仕えることはできない」――は、単なる道徳的教訓ではなく、共同体の存亡に関わる警告である。もし教会が富の論理に従うなら、たとえ立派な建物や組織を有していても、霊的には空洞化してしまう。逆に、富を隣人愛のために用いるなら、小さな共同体であっても神の国の現れとなる。ここに信仰の逆説がある。大きさや豊かさではなく、忠実さと誠実さが共同体の真価を決めるのである。
現代社会は、経済的な価値を唯一の尺度とする傾向をますます強めている。教育、医療、福祉、さらには文化や芸術までもが経済効率で評価される。こうした風潮は、弱者を切り捨て、命さえもコストとして換算する危険を孕んでいる。まさにアモスが語った「履き物一足で貧しい者を買う」という現象が形を変えて繰り返されているのである。教会はこの流れに無自覚であってはならない。富が絶対化される社会において、神に仕える共同体としての道を歩むことが求められている。
では、その道はどのように具体化されるのか。第一に、祈りの共同体であること。パウロが勧めたように、為政者を含め、すべての人のために祈ることによって、教会は富や権力の偶像化に対抗する。祈りは人間の力を相対化し、神の正義の前にすべてを置き直す行為だからである。第二に、富の用い方における小さな忠実さである。日常の買い物、時間の使い方、寄付や奉仕など、具体的な行為を通して「神を選ぶ」決断を積み重ねていくこと。そこにこそ富の偶像化を打ち砕く力が宿る。第三に、弱者の声に耳を傾け、それを神の言葉として聴き取る姿勢である。社会の片隅に追いやられた声こそが、神の裁きと憐れみを告げるからである。
共同体としての教会は、富を拒絶するのではなく、それを神の国のしるしとして転用する使命を与えられている。たとえば、教会の献金や資源が、建物の維持だけでなく、貧しい人々のための支援、難民や移民の受け入れ、教育や医療の整備に用いられるとき、そこに「不正の富を用いて友を作る」というイエスの言葉の具体化が見える。富を神とするのではなく、富を通して隣人を結ぶとき、教会は偶像礼拝を超える道を歩む。
ここで忘れてはならないのは、偶像礼拝の危険は外部からではなく、共同体の内部から生じるということである。教会自身が権威や伝統、財産を絶対視し、神よりもそれに仕えるようになるとき、信仰の核心は失われる。だからこそ、私たちは絶えず自己吟味を行い、「誰に仕えているのか」を問わなければならない。富の偶像を打ち砕くのは、単なる批判ではなく、日々の祈りと実践の積み重ねである。
偶像化した富に抗う教会の姿は、社会にとって小さな存在に見えるかもしれない。しかし、その小ささこそが力である。小さな群れであるからこそ、権力や富の誘惑から自由であり、真理を語ることができる。富を超える共同体の道は、規模や勢力ではなく、忠実な信仰の歩みによって切り開かれる。
Ⅴ節 小さな忠実さと永遠の住まい
イエスの譬えが最後に強調するのは、「小さなことに忠実である者は、大きなことにも忠実である」(ルカ16:10)という逆説である。人はしばしば「大きな仕事」や「壮大な使命」に憧れる。しかし福音は、日々の小さな選択の積み重ねこそが、信仰の真価を決定するのだと語る。小さな忠実さは目立たないが、神はそれを見逃さず、そこから永遠の住まいへ至る道を開かれる。
アモスが告発した社会の罪もまた、小さな不正の積み重ねであった。秤をごまかす、不当に価格を操作する、弱者の声を無視する――それらは一つひとつは小さな行為に見える。しかしそれが積み重なるとき、社会全体を蝕み、神の裁きを招く。逆に、小さな忠実さの積み重ねは、共同体を癒し、神の国を映し出す。だからこそ「小さなこと」が軽視されてはならない。
現代社会における小さな忠実さとは、具体的にどのような姿をとるだろうか。たとえば、日々の買い物でフェアトレードの商品を選ぶこと。忙しい生活の中で、弱者や孤独な人の声に耳を傾けること。自分の持つ富や時間の一部を、困窮者や社会的弱者のためにささげること。これらは一見すると取るに足らない行為に見えるかもしれない。しかし、それらの選択が積み重なることで、社会の方向性は確かに変わっていく。
パウロは「すべての人のために祈れ」と命じた。祈りもまた、小さな忠実さの一つである。祈りは一瞬で世界を変える魔法ではないが、私たちの心を変え、隣人との関わり方を変える。小さな祈りの積み重ねが、共同体を「清く、敬虔に落ち着いた生活」へと導く。祈りの積み重ねこそが、やがて社会全体を変革する力となるのである。
イエスが「不正の富で友を作れ」と語ったのは、この小さな忠実さの延長線上にある。富を通じて隣人と関わりを結ぶとき、それは永遠の住まいへの備えとなる。つまり、地上の富を永遠に持ち越すことはできないが、富を用いた愛の行為は永遠に残る。永遠の住まいは、愛の記憶によって築かれるのである。
この視点から見れば、教会が担う日常的な奉仕や交わりの一つひとつが、すでに神の国のかたちを帯びている。困窮する人への食糧支援、礼拝での祈り、訪問や声掛け、献金や奉仕。どれも小さな忠実さにすぎないかもしれない。しかし、それらは神の国における大きな意味をもつ。小さな忠実さが積み重なるとき、共同体は「永遠の住まい」に迎えられる群れへと形成されていく。
忘れてはならないのは、忠実さは完璧さではないということだ。人は弱く、しばしば失敗する。しかし、たとえつまずいても、再び神に立ち返り、小さな忠実さを選び直すことができる。その繰り返しの中で、信仰は深められ、共同体は鍛えられていく。神はその歩みを見ておられ、永遠の住まいを約束してくださる。
Ⅵ節 神の言葉を聞く飢えと教会の使命
アモスの預言には、「主の言葉を聞くことの飢え」(アモス8:11)という衝撃的な警告が記されている。パンや水に飢えるのではなく、神の言葉を求めても得られないという飢饉である。物質的な不足以上に、人間にとって致命的なのは霊的な飢えである。耳に入るのは無数の情報や雑音であっても、心に響く真理の言葉を聞けない。これは古代のイスラエルに限らず、現代社会にも深く当てはまる。
現代人はかつてないほど多くの言葉に囲まれている。ニュース、SNS、広告、映像――私たちは絶え間ない情報の洪水にさらされている。しかし、その中で人間の尊厳を守り、真の平和を告げる言葉はどれほどあるだろうか。効率や利益を最優先する言説の中で、弱者の声はかき消され、正義を求める叫びは雑音とされる。こうして人々の心は「神の言葉の飢え」に陥る。真理に飢え渇く魂に届く言葉が見つからない。これこそが、アモスが語った飢饉の現代的姿である。
この飢えに対して、教会はどのように応答すべきだろうか。まず、礼拝において神の言葉を語り続けること。説教、祈り、聖歌、聖餐――それらは単なる宗教儀礼ではなく、神の言葉を聞く飢えを満たす場である。世俗の言葉が嘘と暴力で満ちているとき、礼拝は真理の言葉が響く場所となる。人々が飢え渇いて集まる場所に、神の言葉は命の糧として与えられる。
次に、教会は沈黙に陥らないことが重要である。アモスが告発したのは、貧者の叫びに耳をふさぎ、安易な「平和」を唱え続ける偽りの宗教指導者たちであった。もし現代の教会が社会的不正や暴力に沈黙するならば、それは神の言葉を聞く飢えをさらに深めるだけである。教会は、耳に心地よい言葉だけを語る誘惑を拒み、痛みを伴う真理を証しする使命を持っている。神の言葉を語ることは、ときに社会の分裂や反発を招く。しかし、それこそが預言者の務めである。
さらに、神の言葉の飢えは、若い世代の間で特に深刻である。彼らは情報に囲まれて育ち、何が真実かを見分けるのに苦しんでいる。希望を語る言葉が見つからず、孤独や虚無感に苛まれる人々が多い。教会は彼らに対して、古びた教義の押しつけではなく、生きた神の言葉を示す必要がある。それは単に知識を与えるのではなく、共に生き、共に問い、共に歩む姿勢の中で伝えられる。神の言葉は、書物の中だけでなく、隣人との関わりの中でも響くのである。
最後に、この飢えに応えるのは、言葉を語るだけでは不十分である。行いを通して証しすることが欠かせない。教会が貧しい人を助け、孤独な人を迎え入れ、平和のために働くとき、その行為そのものが「神の言葉」となる。人々は語られる言葉以上に、行為を通して真理を感じ取る。説教と行いが一致するとき、神の言葉は真に命の糧となり、飢えを満たす。
「見よ、その日が来る」とアモスが語った日を、私たちは避けることができるだろうか。神の言葉の飢えが支配する社会を回避できるかどうかは、教会が語り、祈り、行う勇気を持つかどうかにかかっている。沈黙ではなく証し、偽りではなく真理、無関心ではなく連帯。そこに神の言葉を聞く飢えを満たす道がある。
Ⅶ節 神に仕える自由と小さな群れの希望
ルカによる福音書16章の結びで、イエスは明確に言われた。「あなたがたは神と富とに仕えることはできない」(16:13)。この一文は、私たちの信仰生活を根底から揺さぶる。なぜなら、富を絶対化する社会にあって、神を選ぶことは必ず不利益を伴うからである。世の論理に従えば、富に仕えるほうが安全であり、富を持つ者に従うほうが得策に見える。しかし、イエスはその逆を告げる。富に仕えることは、魂を縛る偶像礼拝であり、神に仕えることだけが真の自由をもたらすのだと。
ここに「自由」という逆説がある。富に仕えるとき、人は欲望と恐怖に支配され、結局は自由を失う。しかし、神に仕えるとき、人はかえって束縛から解放される。これは不思議な真理である。富に頼らずとも生きられると知るとき、人は富に縛られない自由を得る。富は必要だが、命の基盤ではない。命の基盤は神の愛と憐れみにある。その確信があるとき、人は富を偶像化せず、隣人のために惜しみなく用いることができる。
この「神に仕える自由」を生きる共同体は、しばしば「小さな群れ」に見える。大きな富や権力を持たない教会は、社会から軽んじられることもある。だが、イエスは別の箇所で「小さな群れよ、恐れるな。あなたがたの父は喜んで御国をくださる」(ルカ12:32)と語られた。小ささは無力の印ではなく、神の国を受け継ぐ条件である。小さな群れは、富の偶像に支配されない自由を持ち、真理を語る使命を担う。
現代の教会も、この小さな群れとしての自覚を新たにする必要がある。社会の富や権力に迎合し、存在意義を経済的価値で測ろうとするとき、教会は本来の自由を失う。むしろ、社会の周縁で弱者と共に立ち、真理を語り、祈りを続けるとき、教会はその小ささの中に大きな希望を抱くことができる。小さな忠実さを積み重ねる群れこそが、神の国のしるしを示すからである。
富と神の間で選択を迫られるとき、教会が神を選び続ける勇気を持つならば、たとえ規模は小さくても、社会に対して大きな証しを立てることができる。その証しは、富に仕えることが当たり前とされる世界に対して、別の道があることを示す。すなわち「神に仕える自由」である。この自由こそが、人間の尊厳を守り、社会の希望をつなぐ力となる。
結語 神に仕える自由を選び取る
秋の深まりとともに、今年も収穫の季節を迎えている。実りの豊かさの陰で、災害や格差に苦しむ人々が存在することを思うとき、アモスの言葉が鋭く響く。「弱い者を踏みにじり、貧しい人を押しつぶす者よ」(アモス8:4)。この告発は古代のイスラエルだけでなく、私たちの社会をも貫いている。富と効率を優先するあまり、命や尊厳が軽んじられる時代に、教会は神の言葉を告げる預言者の務めを与えられている。
パウロがテモテに命じた「すべての人のための祈り」は、今日の教会においても決定的に重要である。権力者のためにも祈るとは、彼らの行いを神の御前に差し出し、正義と平和にかなうようにとりなす行為である。祈りは無力ではない。むしろ祈りこそが、社会を神の義に引き戻す力を持つ。沈黙ではなく祈り、無関心ではなくとりなし。その営みの中で、教会は公共的な使命を果たしていく。
ルカ福音書の譬えは、私たちに「富の試金石」を突きつける。不正の富をどう用いるのか、小さなことに忠実であるか否か。これらは日常の選択において具体的に問われる。買い物一つ、時間の使い方一つ、弱者に差し伸べる手一つ――その小さな忠実さが積み重なるとき、神の国のしるしが現れる。永遠の住まいは、大きな偉業ではなく、小さな忠実さの集積によって築かれる。
「あなたがたは神と富とに仕えることはできない」とイエスは断言された。この言葉は厳しいが、同時に希望の言葉でもある。富の偶像から自由になり、神に仕えるとき、人は真の自由を得る。小さな群れに見える教会も、その自由を生きることによって、社会に希望を告げる存在となる。富を絶対化する時代に、神を選び取る自由。それこそが、信仰共同体の最大の証しである。
私たちの前には、常に二つの道がある。富に仕える道と、神に仕える道。その選択は日々の小さな場面で問われる。教会は、小さな忠実さを積み重ねる群れとして、祈りと証しを続ける使命を担っている。神の言葉に飢える時代にあって、沈黙せず、希望を語る群れでありたい。
――主よ、富に縛られる私たちを解き放ち、あなたに仕える自由を与えてください。
――主よ、小さな忠実さを積み重ね、永遠の住まいに迎え入れられる群れとしてください。
――主よ、弱者の声を聞き取り、すべての人のために祈る教会としてください。
秋の空に漂う澄んだ風の中で、私たちは新たに決意する。神に仕える自由を選び取り、その自由をもって隣人と共に歩む群れとなろう。小さな群れであっても、神が共におられるなら、その歩みは確かな希望の光を放つのである。