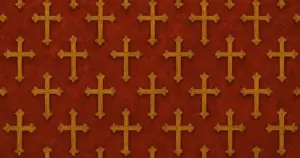聖霊降臨日 説教草稿「低き席に始まる神の国 ― 謙遜と招待の逆説」

【教会暦】
聖霊降臨後 十二主日 二〇二五年八月三十一日
【聖書箇所】
旧約日課:シラ書(集会の書)十章(七‑十一一節), 十二‑十八節
使徒書:ヘブライ人への手紙十三章一‑八節
福音書:ルカによる福音書十四章一, 七‑十四節
【本文】
Ⅰ節 謙遜と招待の逆説
八月の終わり、日本列島は台風の影響で各地に強い雨や風が残る日もあるが、朝晩には確かに涼しさが混じり始めている。酷暑の夏に疲弊した身体に、ほのかな秋の兆しが忍び寄るのを感じる。この自然の移ろいの中に、私たちは人間の営みの限界と同時に、時を超えて働かれる神の御手を思わされる。人間がどれほど自然を制御しようとしても、気候は私たちの思惑を超えてゆく。だからこそ、この時季に聖書が告げる「謙遜」の言葉は、不思議な切実さをもって響く。
旧約日課として与えられたシラ書十章は、人間の傲慢を鋭く告発する。「高ぶりは主と人々を共に憎ませる」(シラ書10:7)。権力者の慢心、金銭や地位に依拠する人間の虚勢――それらは古代の社会に限らず、現代においても繰り返し目にする光景である。近年の政治不信や、社会的格差をめぐる報道に接するたび、私たちはこの言葉をまさに現在の預言として聞かざるをえない。人が自らを絶対化し、他者の声を軽んじるとき、共同体は必ず傷つけられる。シラ書はその危険を冷徹に指摘する。続く節々では、謙遜と知恵がいかに人を堅く支え、共同体を生かすかが語られている。傲慢はやがて根を腐らせ、国をも倒す。しかし謙遜は見えにくい形で共同体を支え、長い時を経て実を結ぶ。これは人間社会の普遍的な真理である。
使徒書であるヘブライ人への手紙十三章も、同じ調子で「兄弟愛を続けなさい」「旅人をもてなすことを忘れてはならない」と語りかける(ヘブライ13:1-2)。ここで勧められているのは、単なる道徳的勧告ではない。信仰共同体の本質そのものを示す言葉である。古代教会の信徒たちは、しばしば迫害や困難の中で暮らしていた。そのときに必要とされたのは、互いに支え合い、見知らぬ者をも受け入れる力であった。愛と歓待は、単なる美徳にとどまらず、生存のための条件だったと言える。著者は「私を決して離れず、見捨てない」と語られる神の約束を想起させる(13:5)。つまり、人をもてなすことは、神に倣う行為である。神が私たちを見捨てず、迎え入れてくださるように、私たちもまた他者を迎える。それこそが共同体を形づくる礎となる。
そして福音書、ルカによる福音書十四章に描かれる場面は、これら二つの声を見事に集約している。イエスはあるファリサイ派の人の家に招かれて食事をされる。人々が上座を選びたがる姿をご覧になったイエスは、「自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる」と語られた(ルカ14:11)。さらに、食事に招く際には、富める隣人や身内ではなく、貧しい人、体の不自由な人、見返りを期待できない人を呼びなさいと命じられる(14:12-14)。これは当時の社会の慣習を根底から覆す逆説の教えである。食卓は本来、身分を誇示し、互いに利害を交換する場であった。しかしイエスはそこに神の国の価値を持ち込まれる。神の国においては、地位や財力は意味を持たない。むしろ、社会の周縁に追いやられた者たちが、真っ先に招かれるのだ。
この三つの聖書箇所に共通するのは、「謙遜と招待の逆説」である。人間の思い込みや慣習とは逆に、神の国では低い者が高められ、受け入れられない者が先に迎え入れられる。現代社会を振り返ると、この逆説がいかに挑戦的であるかを痛感する。経済の効率性が優先され、人間が「生産性」で評価される風潮の中で、弱さを抱える人々はしばしば排除される。教育現場や労働市場での格差拡大も、その一端を物語る。けれども、聖書は告げる。神のまなざしは、排除される者、居場所を持たない者、名もなき者に注がれている、と。
この逆説を信じることは容易ではない。むしろ、現実社会では「上座を選ぶ」誘惑にかられる場面が多い。評価を求め、承認を求め、少しでも高い位置に座ろうとする。それが自然な欲望だからである。しかし、イエスはあえてそこから降りよ、と言われる。低い席に着きなさい、と。なぜなら、そこに神の国の真理が隠されているからだ。謙遜は自己卑下ではない。むしろ、神の前に自らを正しく置くことであり、その視点から他者を迎えることなのである。
ここで改めて思い起こすのは、先日報じられた移民家族への強制送還の問題である。仮放免中の子どもたちが「眠れないほど不安だ」と訴えたというニュースは、社会が誰を迎え、誰を排除しているのかを突きつけた。イエスの語られた「宴席に貧しい人を招け」という言葉は、単なる宗教的比喩ではない。現実の制度と政策に直結する問いである。社会的に弱い立場に置かれた人を迎えるのか、それとも排除するのか。ここに、神の国と人間社会の価値の差が露わになる。
謙遜とは、自分を小さく見せることではなく、自分の力に固執せず、神の恵みに開かれることである。そして、その恵みは、常に他者を迎え入れる方向へと働く。だからこそ、ヘブライ書は「旅人をもてなすことを忘れてはならない」と語り、ルカ福音書は「報いを受けるのは義人の復活のときだ」と約束する。ここには、社会的効率とは異なる時間感覚が示されている。すぐに利益をもたらすものではなく、未来の神の裁きと復活において顕わになる価値。それを信じて歩むことが、信仰共同体の務めなのだ。
私たちの教会が小さな群れであったとしても、この逆説の真理を証しする使命がある。世間から見れば力を持たず、上座に座ることもできないかもしれない。しかし、その小ささこそが、神の国のしるしとなる。謙遜に他者を迎え、招待の輪を広げること。そこに、シラ書とヘブライ書とルカ福音書が一貫して告げる「神の知恵」が輝いている。
Ⅱ節 食卓と共同体の再定義
食卓という場は、単なる飲食の場を超えて、人間社会の秩序を映し出す鏡である。古代ユダヤ社会においても、誰を招くか、どの席に座るかが、その人の社会的地位を示す重要な指標であった。食卓は友好と結束を確認する場であると同時に、排除と差別を強化する場でもあった。イエスがルカによる福音書十四章で語られた言葉は、その慣習の根を揺るがす挑戦であった。すなわち、「貧しい人や体の不自由な人を招け」という命令は、食卓を権力の象徴から解放し、神の国のしるしとして再定義するものであった。
この逆説は、シラ書の語る「謙遜」とも深く響き合う。シラ書は「主が高ぶる者を引き倒し、謙遜な人を高められる」と語る(シラ書10:14)。つまり、食卓における序列の転倒は、単なる礼儀の問題ではなく、神の裁きと救いの秩序を先取りする行為なのである。人が作り上げた優劣の図式を破壊し、神の目から見た真実の序列を示す。それは、やがて来る神の国の預言的な実践にほかならない。
私たちの現代社会においても、食卓の意味は軽んじられてはならない。家族の食卓は、単なる栄養補給の場ではなく、世代をつなぎ、人と人とを結ぶ場である。しかし、現代の都市生活の中では、その食卓が失われつつある。孤食や個食が進み、家庭の中でさえ共同性が希薄になっている。さらに社会全体を見渡すと、貧困や格差によって「食卓に着く権利」を奪われた人々が増えている。子ども食堂や炊き出しの現場は、その現実を鋭く示している。食卓は今もなお、誰が受け入れられ、誰が排除されるのかを問う現場なのである。
ヘブライ人への手紙十三章の「旅人をもてなせ」という勧めは、この文脈で新たな意味を帯びる。旅人は常に不安定で、居場所を持たない存在である。現代における旅人とは、必ずしも物理的に旅をする者だけではない。難民、移住者、仮放免中の人々、あるいは家庭を失った子どもたちもまた「旅人」と呼びうる存在である。彼らをもてなすことは、単なる善意の施しではなく、神の国の食卓を先取りする行為である。なぜなら、神の国は「排除される者が迎え入れられる場」として開かれているからだ。
ルカ福音書の言葉を聞くとき、私たちはつい「上座を譲ることが美徳だ」と道徳的に理解してしまいがちである。しかしイエスが語られたのは、もっと根本的な価値の転換である。上座に座ること自体を拒み、見返りを求めない交わりを築け、という逆説である。これは現代社会の論理――成果主義、効率主義、損得勘定――と真っ向から対立する。だからこそ、この逆説を信じて実践することは容易ではない。むしろ無駄に見え、非効率に見える。しかし、そこにこそ神の国の真理が隠されている。
近年のニュースを振り返れば、私たちの社会がいかに「誰を招き、誰を排除するか」という問いに直面しているかがわかる。難民受け入れの是非、生活困窮者への支援、障がいを持つ人々への制度的保障。これらはすべて「食卓に誰を招くか」という問いの現代的表現である。もしも私たちの社会が、強い者や富める者だけを優先的に迎え入れるならば、それはルカ福音書の語る「この世の宴」と同じに過ぎない。しかし、もしも弱い者、見返りをもたらさない者を迎え入れるならば、それは神の国のしるしとなる。
ここで改めて、教会の使命を考えたい。教会は単なる宗教的組織ではなく、神の国をこの地に先取りする共同体である。だからこそ、教会の食卓――すなわち聖餐の食卓は――誰にでも開かれていなければならない。洗礼を受けた者だけが集う秘儀でありながら、その中心にあるのは「すべての人に開かれるキリストの招待」である。この逆説をどう生きるか。排除の論理に抗い、迎え入れること。それが、食卓と共同体を再定義する道なのである。
結局のところ、食卓は人間の欲望と神の招きが交差する場である。人間はどうしても高い席を求め、見返りを期待する。しかし神は、その座を空にし、低い席に座るように命じられる。そして、その席でこそ、新しい共同体が始まる。謙遜と招待の逆説は、ただの理想論ではない。それは日々の食卓に、礼拝に、社会の隅々に生きて働く神の力の現れなのである。
Ⅲ節 権力と謙遜 ― 支配ではなく奉仕の道
シラ書十章には、権力者への厳しい警告が繰り返されている。「高ぶることは人を根こそぎにする。国々は傲慢のために滅び、王座は謙遜によって堅く立つ」(参照:シラ書10:8,14)。この言葉は、古代イスラエルだけでなく、人類史全体を貫く真理を示している。人間が権力を持つとき、しばしばその権力を維持し拡大するために傲慢に陥る。支配を強めるほどに、共同体はひずみを増し、やがて崩壊に向かう。シラ書は、謙遜が支配を超えて共同体を支える唯一の道であると告げる。
現代に目を向ければ、国内外の政治や経済の場においても同じ構図が繰り返されている。権力を握る者が自己の利益を優先し、弱い者を排除するならば、その社会は分裂と不信の中で弱体化する。近年の国際社会を揺るがす戦争や対立もまた、指導者の傲慢に起因することが少なくない。歴史を振り返っても、古代ローマ帝国の崩壊、近代の戦争の惨禍はいずれも権力者の傲慢と無謀が導いたものだった。シラ書の言葉は、歴史的事実によって何度も裏づけられている。
ヘブライ人への手紙十三章は、この権力の問題に対して、別の角度から光を当てる。「指導者たちの生活に注意を払い、その信仰に倣いなさい」(ヘブライ13:7)と語られる。ここで語られる指導者とは、権力を誇る者ではなく、信仰と生活をもって共同体を導いた人々である。彼らは権力者ではなく、模範となる生き方を示す証人であった。その証しの中心にあるのは、「イエス・キリストは昨日も今日も、また永遠に変わることのない方である」(13:8)という確信である。つまり、権力の変転に翻弄されるのではなく、不変のキリストに従って歩むことが共同体の基盤となる。
ルカによる福音書十四章で、イエスが「自分を高くする者は低くされる」と語られたのは、単なる食卓の礼儀作法を超えて、権力と謙遜の逆転を示している。権力を誇る者はやがて低くされ、謙遜に仕える者が高められる。これは社会通念に逆らう教えであり、だからこそ当時の宗教的・政治的指導者たちには受け入れがたいものだった。イエスの十字架もまた、この逆説の極みである。支配の力をもって世界を変えるのではなく、徹底的な謙遜と奉仕によって神の国を開かれた。その道が、弟子たちに託された道である。
ここで私たちは現代社会の問題と向き合わざるを得ない。先日の報道が示したように、難民や移民、非正規滞在者が制度の網の目からこぼれ落ち、強制送還に直面している。そこには「支配と排除」の論理が働いている。国家の秩序や安全を理由に、人を切り捨てる。その背後には、力を持つ者の傲慢が潜んでいる。しかし、聖書が告げるのはその逆である。弱い者を受け入れること、見返りを期待しないもてなしを実践することが、真に共同体を堅く立てる道である。
教会は、この逆説を社会に証しする使命を持っている。教会自身もまた、しばしば権威や制度に依存し、序列を再生産してしまう危険を抱える。だからこそ、常に「権力ではなく奉仕」「支配ではなく謙遜」に立ち返らなければならない。司祭や監督(ビショップ)が持つ権威も、本来は奉仕のための権威である。力を誇示するのではなく、人々を支えるために与えられている。その本質を忘れるとき、教会は権力の論理に呑み込まれ、神の国のしるしを失ってしまう。
シラ書の警告、ヘブライ書の模範、ルカ福音書の逆説は、いずれも同じ一点を指し示している。権力は謙遜と奉仕によってのみ正しく用いられる、という真理である。現代の私たちも、この逆説を恐れずに受け入れたい。社会において力を持つ立場にある者ほど、低い席に座る覚悟を求められている。その姿を通して、共同体は初めて真に生かされるのだ。
Ⅳ節 もてなしと記憶 ― 歴史を担う共同体
ヘブライ人への手紙十三章は、「旅人をもてなすことを忘れてはならない。こうして、ある人たちは知らずに天使をもてなした」(13:2)と語る。ここには、古代の遊牧的伝統が背景にある。荒れ野を旅する人は常に危険にさらされ、他者のもてなしが命を救った。見知らぬ人を迎えることは、単なる親切以上の意味を持ち、神の祝福と直結する行為だった。旧約聖書のアブラハムが三人の客人をもてなし、その中に神の訪れを見いだした物語(創世記18章)は、その典型である。
イエスの言葉における「招待」も、この伝統の延長にある。ただしイエスは、それをより徹底的に逆説化された。アブラハムは富める家の族長として客人を迎えたが、イエスは「貧しい者、体の不自由な者、盲人、足の不自由な者を招け」と命じられる(ルカ14:13)。つまり、もてなしは単なる善行ではなく、神の国を証しする預言的な行為とされたのである。見返りを求めないもてなしの中に、神の国の秩序が現れる。これは、シラ書が語る「高ぶる者は低くされ、謙遜な者が高められる」という逆説と軌を一にする。
現代の私たちにとって「もてなし」は、観光やサービスの文脈で語られることが多い。しかし聖書のもてなしは、商品化された接待ではない。それは共同体の生命線であり、神の訪れを受け入れる行為である。だからこそ、もてなしは「記憶」と深く結びつく。過去の世代が受けたもてなし、救われた経験が共同体に記憶され、次の世代へと受け渡される。ヘブライ書が「囚人を思いやれ」(13:3)と勧めるのも、共同体の記憶を担うよう促す言葉だ。困難の中にある者を忘れずに覚えることは、共同体の歴史を守る行為なのである。
この点で、現代日本の社会状況を思わされる。近年の入管行政において、仮放免中の子どもや家族が突然強制送還される事例が報じられている。彼らは、社会の記憶から消されやすい存在である。しかし、聖書は「忘れるな」と告げる。見知らぬ者、弱い者を迎えることを通して、共同体は自らの記憶を豊かにし、神の国のしるしを担うのである。逆に、弱い者を切り捨てる社会は、未来を担う記憶を失い、自らを貧しくする。
礼拝における聖餐は、この「もてなしと記憶」の究極の形である。教会がパンと杯を分け合うとき、そこには二つの次元が同時に存在する。一つは「もてなし」である。主イエスが「来なさい」と招かれ、誰もが受け入れられる食卓が広がっている。もう一つは「記憶」である。「私を記念してこれを行え」と語られた主の命令に従い、共同体は歴史を超えてイエスの死と復活を覚える。聖餐において、教会はもてなしと記憶を一体化させ、神の国の預言的なしるしとなる。
シラ書の警告もまた、この構図に重なる。高ぶる者は過去を忘れ、謙遜な者が歴史を受け継ぐ。権力は記憶を改ざんしようとするが、謙遜は痛みを抱えながら記憶を保持する。だからこそ、謙遜な共同体は歴史を担うことができる。ヘブライ書の著者が「指導者たちを思い起こせ」と語るのも同じである。信仰の先人の記憶を忘れず、彼らの生を思い起こすことが、共同体を強めるのだ。
現代の教会も、この召命に応答する必要がある。戦争の記憶、社会的排除の記憶、差別の記憶を忘れずに抱えること。被害者や弱者の声をもてなし、共同体の中に記録すること。それは単なる歴史保存ではない。神の国の証人として、もてなしと記憶を実践する行為である。忘却が社会を分断するなら、記憶は共同体をつなぐ。もてなしは、その記憶を新たに刻み続ける場となる。
こうして、「もてなしと記憶」は、神の国をこの地に先取りする二本の柱となる。見知らぬ者を迎えるとき、私たちは神の訪れを知らずに受け入れる。そして、過去の証人を思い起こすとき、私たちは歴史を担い、未来へと橋を架ける。ヘブライ書とルカ福音書、そしてシラ書が交差するところに、共同体の使命が浮かび上がる。それは、もてなしを通じて記憶を刻み、記憶を通じてもてなしを実践する共同体として生きることである。
Ⅴ節 神の報いと希望 ― 義人の復活を待ち望む信仰
ルカによる福音書十四章で、イエスはこう結ばれる。「そのとき、あなたは幸いだ。彼らはお返しできないからである。義人の復活のとき、あなたは報いを受ける」(ルカ14:14)。この言葉は、もてなしと招待をめぐる逆説をさらに深める。すなわち、見返りを求めないもてなしは、この世では何の利益ももたらさないように見える。しかし神の前では、その行為が永遠の報いにつながる。ここに「希望」という視点が与えられている。
シラ書十章が語る「高ぶる者は倒れ、謙遜な者は高められる」という逆説は、単に倫理的な警句ではなく、終末的な約束を含んでいる。歴史の中で傲慢な王国や帝国は一時的に栄えても、やがて必ず滅びる。謙遜な者は地上で不遇をかこっても、最後には神の正義によって立てられる。この終末的な確信こそが、共同体を支える希望であった。
ヘブライ人への手紙十三章もまた、この希望を告げる。「私たちはここに永続する都を持たず、やがて来る都を探し求めている」(ヘブライ13:14)。この世の制度や権力は過ぎ去るが、神の国は永遠に続く。だからこそ、信徒たちは地上の権力や評価に依存せず、永遠の報いに目を向けて生きることができる。愛の実践やもてなしが、たとえ目に見える成果を生まなくても、それは神の前で決して忘れられない。この確信が、迫害と困難の時代を生きた初代教会を支えた。
現代社会の私たちは、この「報い」という言葉に違和感を覚えるかもしれない。効率と成果がすべてを左右する世界において、報いはすぐに数値化され、即時に評価される。しかし聖書が語る報いは、そのような短期的な利益ではない。それは「義人の復活」という、神の終末的正義に基づく報いである。人間の目には無駄に見える行為――貧しい人を招くこと、見返りのないもてなし、社会から排除される者を支えること――それらが、神の国において意味を持つ。ここに、信仰の逆説的な希望がある。
この逆説を実際の生活に結びつけるのは容易ではない。現実の社会では、見返りを期待しない行為はしばしば軽んじられる。たとえば、ボランティア活動や支援運動に携わる人々は、「それで生活できるのか」「何の得になるのか」と問われることがある。しかし、イエスの言葉はその問いを超えている。得になるか否かではなく、神の国の価値を生きるかどうかが問われているのだ。
先日報じられた仮放免中の子どもたちの訴えを思い起こすとき、私たちはこの言葉の意味を改めて突きつけられる。彼らを受け入れることは、国家や社会にとって「利益」にはならないかもしれない。むしろ経済的負担や制度的な複雑さを伴うだろう。しかし、聖書は言う。見返りを求めないもてなしこそが、神の前で報いを受ける行為である、と。人間社会の計算では「無駄」とされる行為が、神の国においては永遠の意味を持つ。そこに、信仰の逆説と希望がある。
教会は、この希望を絶えず思い起こす場である。聖餐において私たちは「主が来られるときまで、主の死を告げ知らせる」と祈る。これは過去の出来事を記憶するだけでなく、未来の復活と再臨を待ち望む宣言である。聖餐の食卓は、義人の復活の先取りとしての食卓なのだ。そこに集うとき、私たちはこの世の利益を超えた報いを告げ知らされる。だからこそ、教会は小さくとも、希望の共同体として立ち続けることができる。
結局、イエスが告げられた「義人の復活のとき、報いを受ける」という約束は、信仰の核心に触れている。それは、神の国の時間感覚に生きることだ。人間の時間が短期的な成果を追い求めるのに対し、神の時間は永遠を見据えている。その中で、謙遜ともてなしは報われる。だからこそ、私たちは恐れずに「無駄に見える愛」を実践することができる。それが神の国の証しであり、未来への希望を生きる道なのである。
Ⅵ節 小さな群れの使命 ― 世界に向かう教会
ここまで見てきたように、シラ書は人間の傲慢を戒め、謙遜に生きる者こそが堅く立つと語った。ヘブライ人への手紙は、愛ともてなしを絶えず実践し、信仰の先人を思い起こすよう勧めた。ルカによる福音書は、イエスの言葉を通して「高ぶる者は低くされ、低くされる者は高められる」と告げ、さらに「貧しい者を招け」と徹底した逆説を示した。これら三つの聖書箇所を合わせて読むとき、そこに浮かび上がるのは、「小さな群れ」としての教会の使命である。
教会は決して社会的に大きな力を持つ集団ではない。むしろ少数派であり、声がかき消されやすい存在である。日本におけるキリスト者の割合はごくわずかであり、教会はしばしば「小さな群れ」として自らの立場を自覚せざるを得ない。しかし、聖書は繰り返し語る。神の国は小さな群れに委ねられているのだ、と。力や数の大きさではなく、真理を語り、謙遜を生き、見返りを求めないもてなしを実践することにこそ、神の国の証しがある。
ルカによる福音書で、イエスが弟子たちに「小さな群れよ、恐れるな。あなたがたの父は喜んで神の国をくださる」(ルカ12:32)と語られた言葉は、このことを鮮やかに示している。教会が社会的に弱く見えても、神の国の力はその小ささを通して働く。小さな群れだからこそ、権力に縛られず、自由に真理を語ることができる。小さな群れだからこそ、強者ではなく弱者に寄り添うことができる。小さな群れだからこそ、見返りを求めず、無償のもてなしを実践できる。
現代社会において、この「小さな群れ」の使命はますます重要になっている。経済格差が拡大し、社会的排除が進む中で、多数派の論理はしばしば弱者を切り捨てる方向に傾く。先日報じられた仮放免者の強制送還の問題は、その典型的な例である。制度の安定や効率を優先するあまり、人間そのものの尊厳が軽視される。しかし、聖書の語る小さな群れは、その逆を証しする。迎え入れること、共に生きること、見返りを求めないこと。そこに、神の国の秩序が映し出される。
教会はまた、記憶を担う共同体でもある。戦争の記憶、差別の記憶、社会的排除の記憶を忘れずに抱えることは、少数派だからこそ担える使命である。多数派はしばしば不都合な記憶を忘却し、美化する。だが、小さな群れは痛みを覚え続け、祈り続ける。ヘブライ書が「囚人を思いやれ」と勧めるように、見えない痛みに寄り添うこと。それは小さな群れの使命であり、神の国の希望を未来に繋ぐ行為である。
さらに、小さな群れは「世界に向かう群れ」である。教会は自らの閉ざされた内輪の共同体ではなく、開かれた食卓として存在する。ルカによる福音書が示すように、招くべき相手は「貧しい者、体の不自由な者、盲人、足の不自由な者」である。つまり、社会の周縁に追いやられた人々こそが教会の真の客人である。教会が自らの安全や伝統に閉じこもるとき、それは神の国のしるしを失ってしまう。むしろ、開かれたもてなしの場として、社会の中で弱い人々に手を差し伸べるとき、教会は神の国を証しするのだ。
この使命は、日本社会の現実においても緊急の課題である。高齢化と孤独、外国人労働者の困難、戦争の記憶の風化。これらに教会が沈黙すれば、小さな群れの存在意義は失われる。しかし、もし教会がこれらの問題に謙遜に向き合い、小さな声に耳を傾け、もてなしと記憶を実践するならば、その小ささこそが神の国の力を証しする。小さな群れは弱いのではなく、むしろ強いのだ。権力に依存しない自由を持ち、神の愛に根ざして行動する強さを持つ。
「義人の復活のときに報いを受ける」という希望は、この小さな群れの使命を支える支柱である。今は無駄に見える行為も、神の前では永遠に記憶される。社会から見れば無力に見える共同体も、神の国の中では力強い証人である。だからこそ、私たちは恐れずに歩むことができる。小さな群れとして、謙遜を生き、もてなしを実践し、記憶を担い、未来に希望を語る。それこそが、教会の召命である。
結語 低き席に始まる神の国
八月の終わり、日本列島には台風が通り過ぎ、各地に豪雨の爪痕が残った。猛暑の夏に耐えた人々の上に、ようやく秋の涼しさが忍び寄りつつある。自然の移ろいの中で、私たちは人間の営みの脆さを知る。権力も富も、自然の力の前では無力である。だが、その無力を認めるときにこそ、神の恵みが鮮やかに浮かび上がる。低き席に座ること、謙遜に歩むこと、弱い者を迎え入れること――そこから神の国が始まるのだ。
シラ書は、人間の傲慢が共同体を滅ぼし、謙遜が国を堅く立てると告げた。ヘブライ書は、兄弟愛を続け、旅人をもてなし、囚人を思いやるように勧めた。ルカ福音書は、イエスが語られた逆説の真理を記す。「自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高められる」「見返りを求めず、貧しい者を招け」。三つの聖書箇所は、異なる時代と背景を持ちながらも、共に「低き席に始まる神の国」という一点を示している。
現代社会において、この逆説はなお挑戦的である。効率と成果がすべてを決める世界の中で、見返りを求めない行為は無駄に見える。権力を誇り、上座を占めることが当然とされる中で、低い席を選ぶことは愚かに見える。しかし、聖書は告げる。神の国の秩序は、この世の価値観を逆転させる。弱い者を迎えることが共同体を強め、謙遜が未来を築き、無駄に見える愛が永遠に報いられる。これこそが信仰の逆説である。
先日のニュースで、仮放免中の子どもたちが「眠れないほど不安だ」と訴えたことが伝えられた。彼らを迎えることは、国家や社会の論理では非効率かもしれない。しかし、聖書の言葉は明確だ。「旅人をもてなすことを忘れるな」「貧しい者を招け」。私たちが弱い者を迎え入れるとき、そこに神の国が現れる。見返りのないもてなしが、永遠の記憶となり、神の前で報いられる。だからこそ、教会は小さな群れであっても恐れずに証しし続けるのだ。
低き席に始まる神の国。その席に座ることは、自己卑下ではなく、神の恵みに身を委ねることにほかならない。低き席から見上げるとき、私たちは初めて、互いの顔を正しく見ることができる。強者の視線ではなく、謙遜のまなざしによって。そこにこそ、和解と平和の可能性が開かれる。
教会は小さな群れである。しかしその小ささは、力のなさではなく、真理を語る自由のしるしである。小さな群れだからこそ、権力に依存せず、恐れることなく、「貧しい者を招け」というイエスの言葉を実践できる。小さな群れだからこそ、記憶を抱え、未来に希望を語ることができる。小さな群れだからこそ、無駄に見える愛を喜んで実践できる。
――低き席に座り、謙遜を生きよ。
――見返りを求めず、弱い者を迎えよ。
――義人の復活のときに報いを受ける、その希望を信じて歩め。
この招きに応答することが、今日の教会に与えられた使命である。季節が夏から秋へと移りゆくように、世界の秩序も移ろいゆく。しかし、イエス・キリストは昨日も今日も、永遠に変わることのない方である。その方に従って歩むとき、小さな群れは恐れずに、低き席から神の国の光を証しし続けることができる。