教会時論 2025/12/6「伝統の名を借りた排除を拒む」
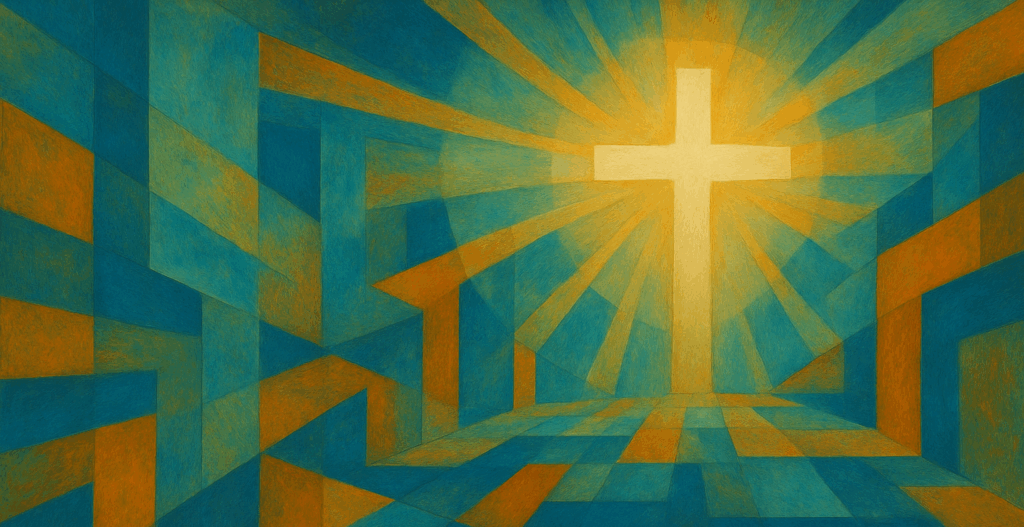
歴史の名を借りた排除を拒む
産経新聞(2025/12/4)社説「『同性婚』認めず — 理にかなう妥当な判決だ」への反論である。本件高裁判決を「理にかなう」と持ち上げる論法は、法の下の平等を矮小化し、国家が特定の家族像を押しつける危うさを看過している。憲法解釈を誤る声に、教会として明確に異議を唱える。
東京高裁は2025年12月4日、同性婚を認めない現行民法・戸籍法を「合憲」とし、原告8人の請求を退けた。判決は憲法24条1項の「両性」を、制定時の慣習に依拠して異性間婚の限定規定と読んだ。その瞬間、傍聴席の空気は重く沈んだ。高裁前に立った原告の一人は、報道陣に向かい「私たちは存在を否定された」と絞り出した。これが今の日本の司法の現実である。産経新聞はこの判決を「歴史的、伝統的婚姻を踏まえた妥当な判断」と称えた。しかし、歴史を理由に人の尊厳を後景に退ける姿勢こそ、社会の根幹を揺るがす。いま問われているのは、同性婚の是非ではない。国家が「正しい家族像」を定め、そこから外れる者を排除し続けてよいのかという、人権の根本である。
まず事実を確認する。全国の高裁で続いてきた同性婚訴訟の控訴審は、これまで6件中5件が「違憲」あるいは「違憲状態」と判断してきた。その根拠は、同性カップルが法制度上の保護から排除され、生命に関わる同意手続・相続・税制・医療アクセスなど、生活の基盤がおびやかされている点である。多数の裁判体が一致して見るのは、現行制度が具体的損害を生み、憲法14条の平等原則に反するという事実だ。一方、産経社説は「歴史」「伝統」を繰り返し、個々の当事者に降りかかる損害について一切語らない。これは議論の核心を回避している。さらに同紙は「制定当時、同性婚を想定していなかった」と述べ、条文の解釈変更を否定する。しかし、憲法の保障は未来世代へ開かれ、時代とともに読み替えが不可避である。選挙権年齢、身体の不可侵、配偶者暴力の概念——いずれも制定時には想定されておらず、憲法解釈の進化によって権利が確立した。憲法前文の「子孫のために」を、出生能力との結びつきに限定するのも誤りである。家族の形は生物学のみに回収され得ない。この単線的な論法は、子を持たない異性夫婦や不妊治療の現実すら視野に収めていない。
教会はここで基準を明確にする。人の尊厳は生殖能力に由来しない。愛し合う二人が互いを支え、共同生活を築く自由は、万人に保障されるべき普遍の権利である。産経社説は「国民の家族観に関わる」と警告するが、家族とは国家が定義する制度ではなく、まず当事者の痛みと希望の場だ。判決が示した「同性婚は一つの家族の姿として承認されている」という認識こそ、社会の現実である。これを制度が追認しない限り、不平等は固定され続ける。誤りが生じているのは、①憲法24条を歴史的慣習に閉じ込めて動かさない硬直、②平等権の侵害を「伝統」の名で正当化する政治的言説、③司法が立法の遅延を放置し、弱い立場の人に損害を負わせ続ける構造の三点である。代替案は明確だ。立法府は期限を切って婚姻平等法の審議に入るべきであり、行政は自治体パートナーシップ制度を国水準に統合し、司法は個別具体的損害への救済を重視する判断枠組へ移行すればよい。この連続的な改革を選ばない限り、日本は人権保障において国際水準から後退し続ける。
ゆえに結論として命じる。国会は2026年会期中に婚姻平等の法案を提出し、審議と採決を完了せよ。行政は当事者の生活を守る暫定措置を直ちに講じ、読者は身近な偏見に沈黙せず、良心に従って声を上げよ。教会は祈りを行動と結び、排除されてきた隣人と共に立つ責務を負う。
「正義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むこと」(ミカ書6章8節)

