牧者雑記「聖書は“同性婚”をどう語り得るのか — テキストの限界と福音の核心」
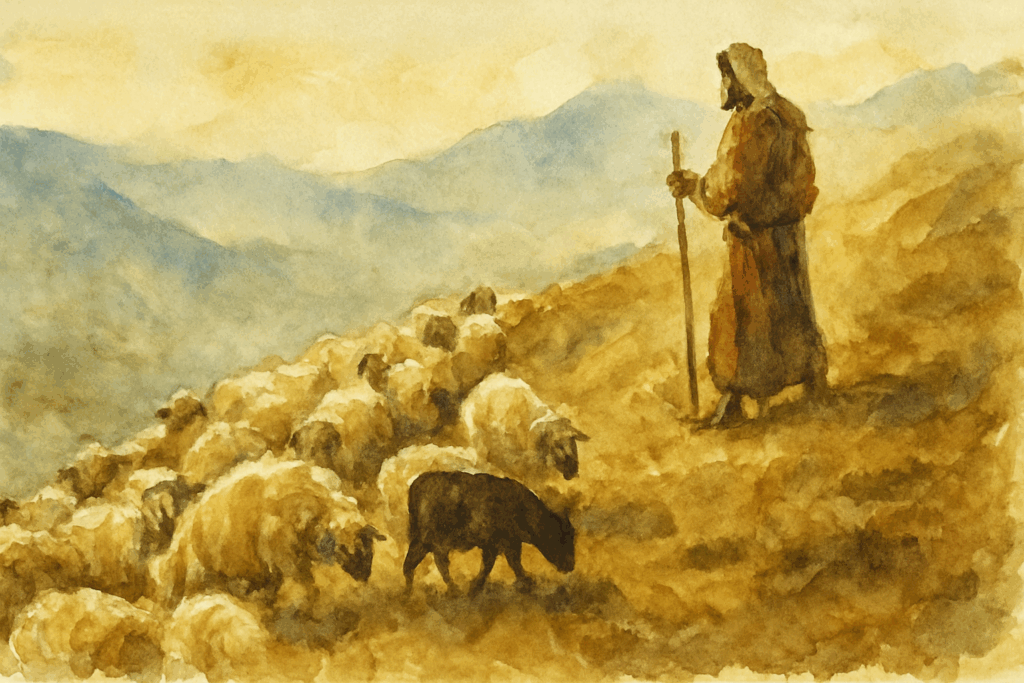
聖書は“同性婚”をどう語り得るのか — テキストの限界と福音の核心
聖書が今日の意味での「同性婚」を直接論じていない。まず、この一点を正確に押さえない限り、議論は常に空転する。なぜなら、旧約・新約いずれの時代も、“婚姻”は家産継承・氏族連結・同盟形成という社会制度の核であり、個人の相互献身や人格的パートナーシップを軸に据える現代の婚姻概念とは、前提そのものが異なるからだ。したがって、聖書に「同性婚」が明示的に否と書いてある、あるいは肯と書いてある、と断定するのは、学問的に不誠実である。
とはいえ、肝心なのはここからだ。テキストが直接言及しない領域で、私たちは何を基準に判断するのか。これは倫理学・聖書学双方の核心に触れる問いになる。まず、古代の同性愛関連の記述は、いずれも“権力と暴力”“支配と屈服”“偶像祭儀との混淆”を問題にしており、現代の自由な成人同士の相互同意的パートナーシップとは、文脈的に全く接点がない。創世記19章、士師記19章、ローマ1章、コリントやテモテにおけるパウロの用語。いずれも、今日の意味での「相互性・忠実・献身」を前提とした関係を想定していない。したがってこれらを「同性婚」の直接的根拠に転用するのは、学問的には成立しない。
問題はむしろ、「聖書全体の物語が何をめざすのか」という大局に置かれるべきである。聖書は、人が孤独に放置されることを神は望まれないという確信から始まる(創世記2:18)。それは一定の“形式”に拘束される前に、人が関係性の中で命を育み、互いを助け合い、信頼と契約に生きることが神の御心だという宣言である。では、もし二人の人間が、性別を問わず、互いに献身と責任と誠実をもって結び合おうとするなら、それは神が祝福する「契約的・倫理的関係」の一つたり得ないのか。テキストの“字義”ではなく、聖書の“精神”が問うているのはまさにそこだ。
さらに言えば、新約は婚姻を自然的区分としてではなく、「互いに仕え合い、キリストが教会を愛したように愛し合う関係」として再定義した。パウロにとって婚姻の本質は“愛のかたち”であり、エスニック・社会階層・身体の区分をすべて超えて人を包み込むキリストの愛が、倫理の基準になる。ゆえに、今日の同性婚を論じる際、決定的に重要なのは「この関係は、互いの尊厳・自由・誠実を実らせるのか」という福音的判断である。
聖書学の視点から明らかなことを、あえて一文でまとめるならこうなる。
聖書は同性婚を語っていない。しかし、聖書が人間関係に求める基準 — 尊厳・忠実・相互献身 — に照らすなら、性別を理由に祝福を拒む根拠は存在しない。
そして、牧会者としての結論は実に単純だ。
人が互いを生かしあい、誠実と信頼に立ち、契約的な愛を結ぼうとするなら、そこに神の祝福を認めるのが教会の務めである。神が人に与える賜物と召命は、性の在り方によって減じられはしない。むしろ、誰も排除しない愛にこそ、聖書が示してきた神の心があらわになる。
その核心を見失わない限り、聖書は今日の私たちにも十分に語りうる。
そしてその語りかけは、いつも同じ一点に収斂していく。
—「愛を恐れるな」。(俊)

