教会時論 二〇二五年九月七日 日曜日 「最も小さい者を守る社会へ―防災・共生・記憶をつなぐ信仰の視座」

はじめに 弱き者の側から社会を問う
聖霊降臨後第十三主日、私たちは再び時論を共有する場に集う。教会の説教は聖書を解き明かすだけでなく、社会のただ中で揺れる現実に応答する責務を負う。災害列島に生きる私たちにとって、防災と減災は抽象的な課題ではなく、日常の延長にある切実な務めである。同時に、入管政策の強硬化や外国人排斥の風潮は、隣人と共に生きる社会の基盤を揺るがしている。そして戦後八十年を経てもなお、海底や南洋の土の中から発見され続ける遺骨は、国家が果たすべき責任を突きつけている。
これら三つの素材に共通するのは、社会の周縁に置かれた人々が見過ごされやすいという現実である。避難所で孤立する高齢者や障害者、強制送還に脅かされる移民、忘却の彼方に置かれた戦時の犠牲者。彼らの声はしばしば政策の中で後景に退き、「例外」とされる。しかし福音は、まさにその例外に寄り添うことを私たちに命じる。「寄留者を虐げてはならない」という旧約の言葉も、「これらの最も小さい者にしたのは私にしたのである」というイエスの言葉も、周縁に立つ人の尊厳を守ることを共同体の中心課題として据えている。
教会は祈りをもって現実を覆い隠すのではなく、祈りをもって現実に立ち向かう共同体でありたい。だからこそ、防災の取り組みにおいては避難所を開き、移民政策においては共生の証人となり、戦争責任においては記憶を語り継ぐ役割を担う。信仰は社会の外にある装飾ではなく、社会を形づくる根幹に関わる。
はじめにあたり強調したいのは、いのちと尊厳を守る姿勢こそが教会の公共的使命であり、また社会を持続可能にする唯一の道だということである。ここから私たちは三つの論点をたどり、結びに共通の核心を見いだしたい。
一.いのちを基軸に据える防災国家へ(災害列島の備えと〈ふつうの暮らし〉の回復)
九月の初め、私たちはまた「備え」を思い起こす。だが、備えの目的は抽象的な「復旧」ではない。壊れた暮らしのただ中にある一人ひとりが、ふたたび台所に火を入れ、職場に向かい、子どもを送り出し、夜には安らかに灯りを落とせる――その具体にこそある。いのちと人権の尊重を第一義とし、〈ふつうの暮らし〉を最短距離で取り戻すこと。これが防災・減災の本丸である。
気候危機がもたらす極端事象は、豪雨も猛暑も同時多発で襲う。地震の国であることに加えて、私たちは今や「多災複合の列島」を生きている。避難所以外での生活を余儀なくされる人への支援の明確化、福祉サービス提供の公的負担――近年の制度改正は前進だが、条文が暮らしを支えたと言えるのは、必要な人の手元に、遅滞なく実務が届いたときだけである。障害や持病のある人、高齢者、乳幼児連れの家庭、ケアの担い手を失った家――弱さを抱えた人ほど、制度の継ぎ目でこぼれ落ちやすい。だからこそ、支援は「申請主義」ではなく「発見主義」でなければならない。戸別訪問と伴走支援、記録と共有、財政の裏付け。現場がすでに始めている地道な営みを、国と自治体は確実に後押しすべきだ。
住まいと生業(なりわい)の再建は、被災者にとって抽象的な「復興」の合言葉よりもはるかに切実だ。仮設から恒久へ、休業から再開へ。その橋を渡すのは祝辞ではない。家屋の耐震・断熱改修に連動した再建支援の拡充、中小企業と個人事業の資金繰りと税制の特例、地域医療と介護の空白を埋める人材派遣――いずれも費用がかかる。だが、社会の脆弱部位をそのままにしておく「見えないコスト」は、次の災害で必ず何倍にも膨らんで戻ってくる。公共投資の優先順位を「ハコもの」から「暮らしの基礎体力」へ。遠回りに見えて、これがもっとも廉価で倫理的な選択である。
都市の高層化は新たな震動リスクを抱える。長周期地震動への備え、既存建築の設備・内装・免震制御の更新、雑居ビルの耐震・火災対策、液状化への地盤改良。行政は「指針」や「努力義務」で満足してはならない。所有者の負担能力に応じた補助・税控除・無利子融資を束ね、実効性のある総点検と改修のパッケージに落とし込むべきだ。学校・病院・社会福祉施設は最優先。そこで働く人とそこに集う人の身の安全が守られなければ、地域の回復は立ち上がらない。
もう一つ、私たちは「動かし続ける防災」へ発想を転じる必要がある。巨大地震の可能性が高まった局面で、社会活動を全面停止するか、すべて通常運転に戻すか――二者択一ではない。イベントであれ鉄道であれ、リスクを見積もり、避難動線と情報伝達を事前に組み込み、止める・縮小する・続けるの選択肢を準備しておく。混乱は情報の曖昧さから生じる。だから、自治体と企業、学校、地域コミュニティが、平時に「状況別台本(シナリオ)」を共有しておくことが肝心だ。判断を慌てて下すのではない。慌てなくて済むよう、先に決めておくのである。
「防災庁」構想が語られるなら、なおのこと問われるのは縦割りの解体と現場主義だ。司令塔は要る。だが、司令塔が上意下達の口だけになれば、末端は動かない。物資・人員・医療・介護・情報・住宅の各ラインを、データ連携で可視化し、自治体間・省庁間・民間との相互運用性を標準化する。そして制度間の狭間にいる人――車中泊、在宅避難、ペット同行、外国籍、DV避難――を最初から対象に含めた設計に改める。練度は訓練からしか生まれない。年中行事の訓練ではなく、現場と同じ複合事象を想定した実動訓練を、予算と時間をかけてやる覚悟が必要だ。
教会は何ができるのか。私たちはしばしば「祈ります」と言う。もちろん祈る。しかし、祈りは手足を伴ってこそ真実になる。礼拝堂は避難者に開かれているか。名簿上の高齢者や独居の仲間に、平時から声をかけているか。非常持ち出しには他者のための余分が入っているか。献金は、疲弊した現場の継続的な伴走に充てられているか。防災は信仰の外側にある業務ではない。〈隣人を自分のように愛しなさい〉という主の命に対する、極めて具体的な応答である。「これらの最も小さい者の一人にしたのは、私にしたのである」(マタイ25章の精神)は、災害時こそ試される。
地域の福祉団体や社会福祉協議会、当事者組織が、自前の資源を持たぬまま献身的に動いている。国はその献身に財政的裏付けを与えるべきだ。ボランティアは無料であっても、移動と宿泊と物資は無料ではない。制度は最後の一人に届くまでは不十分だと自覚し続けたい。とりわけ、広域避難からの帰還を阻む医療・介護の受け皿不足は、生活再建を頓挫させる最大の要因の一つである。人材確保難を理由に諦めるのではなく、応援職員の制度化、家族支援の補助、リモート診療の活用、地域間連携の強化など、できることは多い。
神学の言葉で言えば、希望は偶然の贈り物ではない。希望は仕組みと選択の集積である。備えない社会に希望は宿らない。だから、私たちは「平時の政治」を変えねばならない。気候危機を抑え込むための排出削減と適応策の加速、脆弱性を抱えた人に届く社会保障、地域医療とケアの再設計、住まいの安全とエネルギー効率の底上げ。これらは防災政策の別名であり、同時に、いのちの尊厳を守る政治そのものである。
九月の空は高く、しかし海はなお温い。次の季節風の前に、私たちは何を変えられるか。祈りは私たちを立ち上がらせる。教会が先に動き、自治体と手を結び、企業と学校と協働しよう。〈ふつうの暮らし〉を守ることは、最も聖なる務めの一つである。いのちを中心に据える防災国家へ――その道は、すでに私たちの足もとから始まっている。
二.人権を礎とする共生社会を(強制送還の強化と共生の課題)
日本の入国管理行政に吹く風は、近年ますます冷たさを増している。在留資格を持たない人々を「排除すべき存在」と決めつけるような言説が政治の言葉の中に浸透し、その結果として、強制送還の件数は着実に積み上げられている。だがその陰で切り捨てられているのは、確かにここに生きてきた隣人の物語である。病を抱えた人、学ぶ子どもを持つ親、あるいはすでに日本を「故郷」と感じている若者――彼らは数字の一つではなく、顔と声を持つ人間だ。
「不法滞在者ゼロプラン」と称する政策は、法秩序の名を借りて、国家の強制力を前面に押し出す。その背景には「国民の安全安心」という言葉が繰り返されるが、その「国民」とは誰を指すのか。共に暮らし、働き、税を納め、地域を支えてきた外国籍の住民は、はたしてこの「国民」の円の中に含まれないのか。法の文言が冷徹であればあるほど、そこに欠けている人間性が際立つ。
先日、長く日本人の配偶者と暮らしてきたある外国籍の男性が、裁判の途上で突然に送還された。通知は弁護団にも直前に伝えられ、司法の審理を受ける権利さえ奪われた。この国の法治の根幹を支える「適正手続」の理念は、外国人にとって適用されないのか。人権の普遍性を強調してきた戦後憲法体制の足もとが、今まさに揺らいでいる。
聖書は異邦人の扱いについて繰り返し語る。「寄留の外国人を虐げてはならない。あなたがたもかつてエジプトの地で寄留の身であった」(出エジプト記22:20)。これは古代社会における倫理規定にとどまらない。異なる背景を持つ人と共に生きることが、共同体を豊かにするという普遍的な知恵である。
日本社会は少子高齢化に直面し、労働力不足を補うために多くの外国人を迎え入れてきた。建設現場、介護、農業、製造業、あるいは高度技能分野――あらゆる領域で彼らの働きなしに経済は回らない。それにもかかわらず、彼らが不安定な在留資格のもとで常に「帰れ」と迫られるなら、根を下ろし、地域社会の一員として責任を分かち合うことはできない。
問題は数ではない。人権の軸をどこに据えるかである。政府の論点整理には「社会との摩擦が許容度を超えるなら制限を」とある。しかし「許容度」とは誰が、どの基準で決めるのか。住民の漠然とした不安を「客観的指標」として政策化するなら、それは容易に排外主義に転化するだろう。
欧州諸国もまた、移民・難民をめぐる葛藤を抱えてきた。それでもなお、多様な文化背景を持つ人々を社会の資産とみなし、言語教育や地域統合政策を進める方向へ歩んできた。日本が学ぶべきは「閉じる」ことではなく、「開きながら調整する」知恵である。
共生は容易ではない。文化の違い、生活習慣の衝突、宗教的実践の齟齬――現場には確かに摩擦がある。しかし、摩擦を恐れて入口を閉ざすことは、社会を硬直化させ、やがて自らを孤立させる。多様性は不安の源であると同時に、創造の源泉でもある。新しい発想、未知の可能性、活力ある地域づくりは、異質な存在との出会いから生まれる。
教会の務めはここでも明白だ。異邦人を迎える共同体としての原点に立ち返ることである。礼拝の場は、国籍や在留資格を問わず、すべての人に開かれているか。地域の日本語学習のサポートや生活相談を担える余地はないか。ヘイトスピーチに対して沈黙するのではなく、「すべての人は神の似姿に造られた」と証しする声を上げられるか。信仰共同体が果たす責任は決して小さくない。
「この国に暮らすのは私たちの仲間だ」と言えるかどうか。政治家や行政だけではなく、地域住民一人ひとりの意識が問われている。私たちが外国籍の隣人を「共に担う存在」と見るとき、社会の空気は確実に変わる。
強制送還を数値目標で競うのではなく、一人の人間の生活史を尊重する政治へ。共に住む者の権利を保障する制度を整える政治へ。そこにこそ、真の安全と安心が宿る。
「国民」という言葉が排除の境界線を引くのではなく、「隣人」という言葉が結び直す絆となるとき、この国はより強く、より豊かになるだろう。信仰の共同体から、そして市民社会全体から、その声を発し続けたい。
三.記憶を未来に手渡す責務(戦時遺骨の収集と国家の責任)
戦後八十年を迎えた日本において、なお発掘され続けるのは、地中や海底に眠る人々の遺骨である。歴史は過去の棚にしまわれるものではなく、土や波の中から問いかけてくる現実だ。山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で見つかった人骨は、戦時動員の犠牲がいまだに癒されていないことを示している。朝鮮半島から徴用された人々が危険な坑道で命を落とした事実は、半世紀を超えてもなお、私たちの社会に問いを投げかけている。
戦没者遺骨収集推進法は「国の責務」を明記した。しかしその対象は「戦闘行為による戦没者」に限られると解され、炭鉱事故の犠牲者は外に置かれてきた。だが、国家総動員体制のもとで、軍需のために過酷な労働を強いられた人々の死は、広義の戦没と呼ぶべきではないか。単なる労災として切り捨てるなら、当時の政策責任を曖昧にし、遺族への応答を拒むことになる。
市民団体がクラウドファンディングで資金を集め、潜水調査を重ね、ようやく発見に至った経緯は、国家の怠慢を逆照射する。犠牲者の遺骨を前にしてもなお「危険だから」「対象外だから」と言って調査を回避する政府の態度は、倫理的に看過できない。むしろ国家が率先して技術と資源を投入し、DNA鑑定を含む科学的調査を進めるべきだ。日韓両国の協力は不可欠であり、犠牲者が朝鮮人であるなら返還の責務は明確だ。戦後八十年、国交正常化六十年を迎える今年こそ、真剣な対応が求められている。
海外にも未収容の遺骨は膨大に残されている。硫黄島や沖縄の地上戦跡地、パラオ・ペリリュー島など南太平洋の激戦地――そこには今も数十万柱が眠る。戦友や遺族が高齢化する中で、収容数は減少の一途をたどっている。時間は待ってくれない。米国の機密解除資料をもとに、地図や記録を丹念に照合しながら遺骨を特定する努力も始まっている。科学の知見と国際的協力を総動員することこそ急務だ。
問いは単に「誰の骨か」を明らかにするだけではない。私たちが戦争とどう向き合うのか、その姿勢が問われている。遺骨は沈黙している。だがその沈黙は、国家が背負った歴史的責任を声なき声で告発している。遺族にとって、骨壺に納める行為は、故人を個人として尊重し直す営みである。それを放置することは、人間の尊厳を二度殺すに等しい。
聖書において、骨は単なる遺物ではない。「乾いた骨よ、主の言葉を聞け」(エゼキエル37章)。預言者の前に散らばる骨は、やがて息を吹き込まれて再び立ち上がる民の象徴となった。骨を集めることは、忘却を拒み、共同体を再生する営みと重なる。
戦争責任の処理において、日本社会は長らく「軍人・軍属」中心で制度を組み立て、民間人や動員労働者を周縁に追いやってきた。恩給や補償から外され、記憶からも外されてきた人々。だが彼らもまた国策の犠牲者であることに疑いはない。制度の線引きをそのまま踏襲することは、冷酷な差別の再生産にほかならない。
国は、遺骨収集を「人道上の義務」と明言すべきである。調査に海上保安庁や自衛隊の技術を投入することは、憲法の平和主義と矛盾しない。むしろ過去の戦争犠牲に真摯に向き合うことこそ、平和国家としての道義的基盤を強化する。
教会にとっても、この課題は無縁ではない。戦時下で教会が果たした加担の歴史を忘れてはならない。信仰共同体が率先して追悼を行い、遺族と共に祈り、国家に対して責任ある行動を求めることは、悔い改めの具体的実践である。講壇から「平和」を語るだけでは不十分だ。記憶を守る行為こそ、平和の礎を築く。
「時の壁」が迫るなかで、私たちは未来世代に何を渡すのか。遺骨を集め、身元を確かめ、故郷へ返す。その一つひとつの営みが、戦争の惨禍を繰り返さない誓いを次の時代へと伝える。
記憶を歴史の暗がりに閉じ込めるのではなく、未来を形づくる糧とすること。これこそが、私たちに課された責務である。骨は沈黙している。だがその沈黙を聞き取る耳を持つとき、私たちの社会はようやく、過去に対して誠実になれる。
結語 いのちと尊厳を守る政治と信仰へ
防災、移民、戦争責任――三つの課題は一見すると別々の問題のように見える。だが根底に通底するのは、人間のいのちと尊厳をどう守るかという一点に尽きる。自然災害であれ制度による排除であれ、あるいは戦時の放置された犠牲であれ、共通するのは「弱き者の声が聞き届けられない」という現実である。
防災の名の下に、制度や建物の耐震性だけが議論され、仮設住宅で孤立する高齢者が見過ごされるなら、その防災は空虚である。入管政策が「国民の安心」を繰り返し唱えながら、在留資格を持たぬ人々を人権の外に追いやるなら、その安心は誰のためのものかと問わざるを得ない。戦争の犠牲者を「制度の対象外」として切り捨てれば、記憶と責任の継承は断ち切られ、同じ過ちを繰り返す道を開くことになる。
三つの問題は、私たちが社会の「周縁」に立たされる人をどのように扱うかを照らしている。聖書は一貫して「寄留の者、孤児、やもめを顧みよ」と語る。そこにこそ、共同体の真価が試される。防災計画において、最も弱い立場の人を守る視点を忘れないこと。外国籍の隣人を共に生きる仲間と見なすこと。戦時に命を落とした人の遺骨を、国境を越えて丁重に返すこと。これらはすべて同じ福音の要請から導かれる。
民主主義の政治は、数の多数で正当化されるものではない。声なき声をすくい上げる制度と実践があってこそ、本当の意味で「公共」が成り立つ。公共神学の課題はまさにここにある。信仰共同体は、社会に沈黙を強いられた人々のために代弁者となり、声を合わせて公の場に問いを投げかける。その営みは決して「政治への越権」ではなく、むしろ信仰の核心に属する。
戦後八十年を生きる私たちは、もはや「知らなかった」と言うことはできない。情報は溢れ、科学は進歩し、制度の不備も繰り返し指摘されてきた。問題は「意思」の有無に尽きる。変える意思があるのか。弱き者を見捨てないと決意するのか。その選択は政治に委ねられるだけでなく、市民一人ひとり、そして教会共同体にも問われている。
「これらの最も小さい者の一人にしたのは、私にしたのである」(マタイ25:40)。この言葉を心に刻むとき、防災も、移民政策も、戦後責任も、単なる政策課題ではなく、信仰の応答であることが見えてくる。教会は祈りと行動を結び合わせ、市民社会と共に歩み、政治に責任を問う。そこにこそ、福音が現代に生きる道がある。
いのちを守り、尊厳を回復し、記憶を未来に手渡す。その営みを怠るとき、社会は弱く、空虚になる。逆にその営みに忠実であるとき、社会は強く、豊かになる。信仰に支えられた小さな実践の積み重ねが、未来を形づくる最大の力となる。
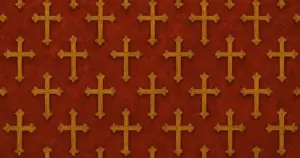

学ぶこと、教えていただくことがとても多いです。